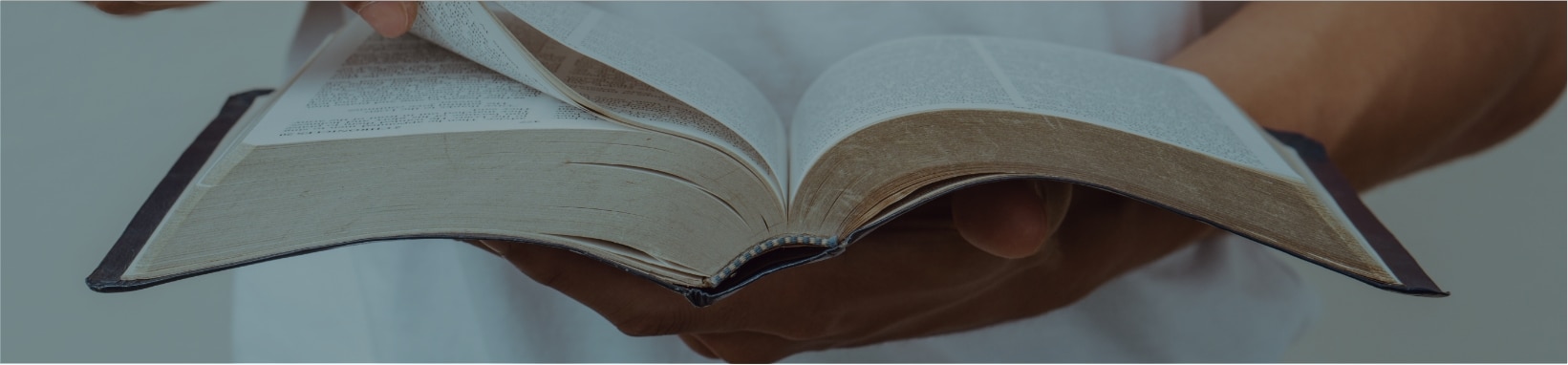【革靴のお手入れ方法】日頃のケアで靴を長持ちさせるコツ
2025.07.29

この記事の所要時間:約7分
革靴は日々のちょっとしたケアと定期的なメンテナンスをすることで、何年・何十年と長く履き続けることができます。
しかし、「どのようにお手入れしたらいいかわからない」や「なんだか難しそう」といったイメージで敬遠しがちですよね……
ここでは誰でも簡単にできるお手入れ方法と革靴が数倍長持ちするようなコツをいくつかご紹介していきます。
お手入れに必要なクリームの種類や特徴について知りたい方は
「革靴クリームはどう選ぶ?種類ごとの特徴と選び方のポイント」 をご覧ください。
1. 革靴のお手入れについて

革靴は、お手入れをしていなければ色が褪せて艶もなくなり、どんどん劣化していきます。
できるだけ長く履き続けるためには、日頃のお手入れが重要です。
1-1. お手入れの必要性
定期的なお手入れは、革靴をきれいな状態でキープするために不可欠な作業です。
お手入れをしないと靴の乾燥が進み、色褪せや色落ち、ひび割れなどの原因となります。
道具を揃えれば自宅でも簡単にお手入れができるので、この機会に隙間時間を使ったケアを始めてみましょう。
1-2. お手入れの頻度
革靴は「月に1度」の本格的なお手入れで美しさを保ち、長持ちさせることができます。
お持ちの靴の数にもよりますが、目安としては同じ靴を8〜10回履いたら1回お手入れするというイメージです。
また、革靴を履いたあとも簡単な日々のケアをしてあげましょう。
過剰なお手入れは革に負担をかけてしまい型崩れを起こしてしまう恐れがあります。頻度を守って正しい方法でお手入れしてくださいね。
1-3. お手入れに必要な道具

① 馬毛ブラシ(ホコリ落とし用)
② 豚毛ブラシ(クリームを馴染ませる用)
③ 汚れを落とすクリーナー
④ シューズクリーム
⑤ クロス(なければ古布でも代用可)
⑥ 仕上げ磨き用のグローブ
⑦ 木製のシューズキーパー
2. お手入れ方法
ここでは、月に1度の「本格的な靴磨きのお手入れ方法」と、履いた後の「日々のケア」について詳しく解説します。
2-1. 本格的なお手入れ方法
お手入れというと面倒な作業のように感じる方もいらっしゃるかと思いますが、慣れてしまえば10分ほどで完了します。
履く頻度にもよりますが、1ヵ月に1回程度はしっかりと磨くようにしましょう。
そうすることで革に栄養が行き渡り、見違えるほどきれいになると同時に長持ちするようにもなります。
1.馬毛ブラシでホコリを落とす

ブラシで靴全体をブラッシングしてホコリを落とします。
まずは、かかとからつま先側へ縦方向にブラシをかけましょう。
また、甲部分は横方向へブラシを動かすのがきれいに仕上げるコツです。あまり力を入れる必要はありません。
また、靴のフチの部分はホコリが溜まりやすいので重点的に。靴シワの方向に沿ってブラシがけをするのがポイントです。
2.クリーナーで汚れを落とす

クロスを2本の指にフィットするように巻き、クリーナーをクロスによく馴染ませ、靴全体をこすりすぎないように軽く拭いて汚れを落とします。
クリーナーは100円玉1個分くらいが適量です。
クロスを介さず直接靴に塗ったり、クリーナーを大量に塗ったりしてしまうと、部分的にしみになる可能性があるため注意しましょう。
3.シューズクリームを塗り込む

シューズクリームを米粒3〜4粒分ほど取り、ふたの裏側でよく馴染ませてから靴全体にまんべんなく塗り、革に色・栄養・艶を与えます。
シューズクリームには保湿だけでなく補色の効果もあるため、同色系統か少し薄い色のクリームを選ぶのがおすすめです。
4.豚毛ブラシで馴染ませる

塗ったクリームを浸透させるために、汚れ落としとは違う豚毛ブラシでクリームを均一に伸ばす。
ブラッシングで熱が革に伝わるようにすると、ツヤが出ますよ。
5.グローブで仕上げの磨き

お手入れの最後に、靴磨き用グローブに手を入れて、乾拭きします。
余分なクリームは取り除いて、ツヤを出して完了です。
2-2. 履いた後のケア
家に帰宅し、履いた革靴を玄関にそのまま放置していませんか?
革靴を1日履いて外出すると、ホコリやチリが靴に付着します。そのままにしておくと、革の水分や油分を奪い取り、乾燥の原因に。
それを防ぐためには、帰宅後のちょっとしたケアをしてあげることが重要です。
手間なく簡単にできるので、靴を美しく長持ちさせるためにも、日々のケアを継続して行いましょう。
1.ブラッシングでホコリを落とす

ブラシで靴全体をまんべんなくブラッシングして表面をきれいにします。ホコリやチリをしっかり掻き出しましょう。
革靴用のブラシには馬毛と豚毛がありますが、日々のお手入れで使うブラシは柔らかい馬毛ブラシがおすすめです。力を入れすぎると傷ができる可能性があるため、やさしく丁寧に磨きましょう。
2. 細かい汚れをふき取る
ブラシで磨いたあと、さらに気になる細かい汚れがあれば、クロスで拭いていきます。
クロスはコットン100%のものが柔らかく、革が傷付かないためおすすめです。
3.シューズキーパーを入れる

シューズキーパーには、除湿・脱臭・型崩れ防止の効果があります。左右の形を確認し、つま先方面にぐっと押し込みながら、革のシワがしっかり伸びるようなイメージで挿入します。
帰宅後のケアはたった2STEPで完了です。
日々のお手入れは大切ですが、毎日クリームを塗る過度に手入れをしてしまうと逆に革を痛めてしまいます。軽めのお手入れで済ませましょう。
3.お店に依頼するのはどのようなとき?
日々のケアは自分でおこなえば十分ですが、大切な用事や気分を引き締めたいときなどにはお店にメンテナンスを依頼しましょう。
プロへの依頼にはお金がかかりますが、自分では気付けなかった傷みや不具合まで徹底的にケアしてもらえます。返却時には段違いにピカピカになっているので、革靴を長持ちさせたい場合や大切なシーンなどではお店に依頼するのがおすすめです。
4. 革靴を長持ちさせるコツ

履けば履くほど傷んでしまうのは仕方ないことですが、ちょっとした気遣いで靴を長持ちさせることができます。
長持ちさせるコツを習慣化して、お気に入りの靴を長く愛用してください。
4-1. 毎日同じ靴を履くのはNG

1日履いたら1~2日ほど休ませ、1週間で2~3足を交代で履くようにするのが鉄則です。
人は1日にコップ1杯の汗を足からかくといわれ、革靴は湿気が乾くまでには半日〜1日ほどかかります。
連日湿った状態で靴を履くと劣化を早め、寿命を縮めることになるので休ませてあげることが大事です。
4-2. 靴を履くときの注意点
あなたは靴を履くとき、指を入れていませんか?
靴べらを使わず無理に足をぐりぐり押し込んで履くと、靴のかかと部分に負担がかかり、内側の革が伸びたり、摩擦で破れたり、糸がほつれたりしてしまい型崩れをおこす原因になります。
革靴のかかと部分は傷みやすいので、革靴を履くときは「靴べら(シューホーン)」を使用してください。

4-3. 靴を新しく購入したときのケア
購入したばかりの靴の革は乾燥しています。そのままの状態で靴を履いてしまうとシワの部分にひびが入り、水分が染み込んでしまうため、シミができてしまう恐れがあります。
履き下ろす前に以下のお手入れをしておきましょう。

- ひび割れを防ぐために、シュークリームを塗って保湿する
- シミを出来づらくするために、防水スプレーを振っておく
4-4. たまにしか履かない靴の保管方法
靴を長期間保管する際は、お手入れをしてからしまってあげると、カビの発生や型崩れを防ぎ、靴の負担を軽減できます。
まず、定期的なお手入れをします。次は、靴にシューズキーパーを入れ、ホコリがつかないよう通気性のよい袋(購入したときに付属されている袋)に入れて保管しましょう。袋がない場合は、箱を代用してもOKです。箱にしまっておく際は、除湿剤や乾燥材を一緒に入れておくとカビ予防になります。

また、木製のシューズキーパーは湿気やカビの対策にもなります。
長く履いていない靴は水分・油分が失われているため、デリケートクリームを使い保湿をしてから保管しましょう。
5. まとめ

いかがでしたか?
靴をきれいな状態で長持ちさせるには以下のポイントを行いましょう。
- 月1回の頻度で時間をかけて靴を磨く
- 履いたあとは毎回簡単にお手入れをする
- 靴は2~3足用意しておき、1日~2日違う靴を履く
- 革靴を履く際、靴べらを使用する
革靴はしっかりとお手入れすれば何年も履くことができます。
愛着の湧いたお気に入りの靴をずっと履き続けられるように、定期的なお手入れと日頃のほんのわずかな気遣いを怠らないようにすることが大事ですよ。