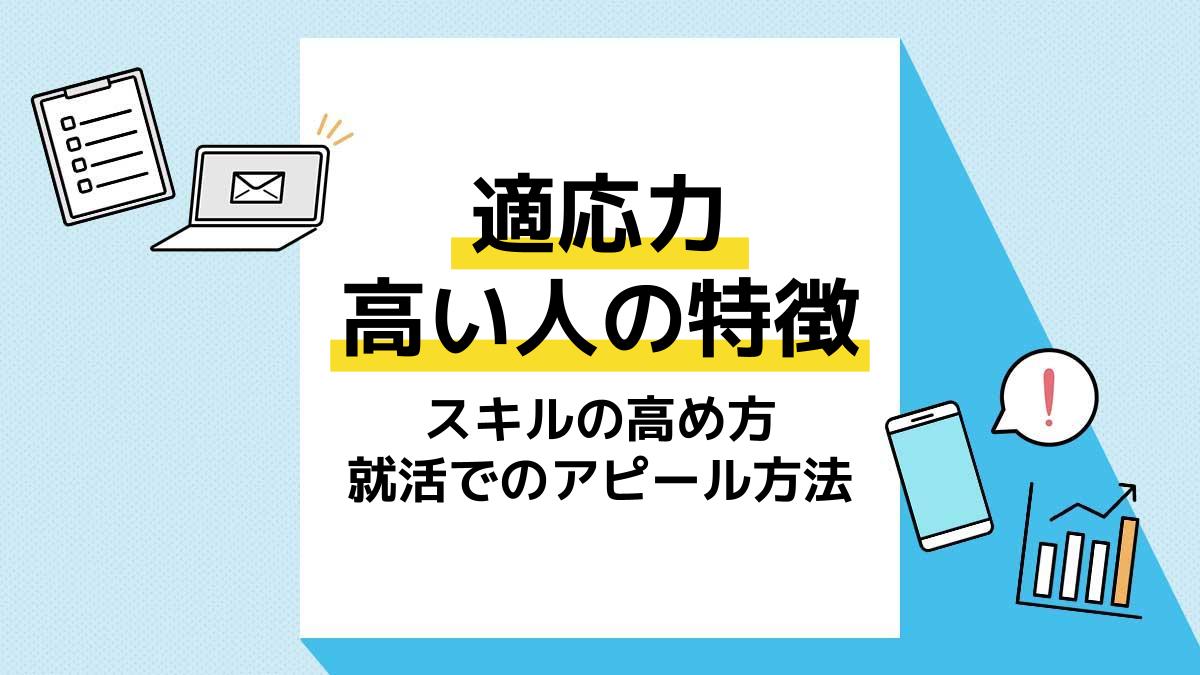適応力(てきおうりょく)とは、環境に応じて、行動や考え方を切り替える能力を指します。適応力が高ければ、仕事とプライベートどちらでもよい影響が期待できるでしょう。
「環境に素早く馴染めない」「初めての人とうまく会話ができない」など悩む方もいるかもしれませんが、考え方や行動次第で適応力を高めることはできます。
この記事でわかること
- 適応力は、変化が激しい昨今に対応するために必要なスキルのひとつ
- 適応力を高めることで、変化や慣れない場に対するストレスを軽減できる
- 適応力の高さは、就活の自己PRや長所でアピールすることができる
適応力の意味とは
適応力とは、環境に応じて、行動や考え方を切り替える能力です。次のような思考・行動ができる方は、適応力があるといえるでしょう。
- 急にやり方が変わってもストレスを感じにくい
- 初めての場所、人間関係でも、自分らしく行動できる
- 予想外のことが起きても、冷静に行動できる
適応力と似た言葉の意味
適応力と似た意味をもつ言葉は、複数存在します。似た言葉とその意味は次のとおりです。
| 「適応力」と似た言葉 | 意味 |
|---|---|
| 順応性・順応力 | 環境の変化にあわせて 変わることができる能力 |
| 柔軟性 | 状況に応じて 素早く変化できること |
| 臨機応変 | その場に応じて 適切な行動ができること |

長所をアピールするとき、適応力のほか、これらの言葉を用いて自分の特徴を伝えることができます。
-
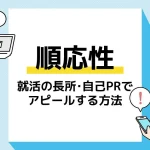
-
順応性とは?メリットや類義語と就活で長所・自己PRとして伝える例文を紹介
順応性(じゅんのうせい)とは、環境や状況の変化にすぐ対処できる性質を指します。新しい職場、人間関係に慣れるまでの時間が早く、その人のメリットにもなります。順応性の高さは長所や自己PRとしてアピールすることも可能です。
続きを見る
-
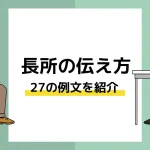
-
【例文27選】就活での長所の見つけ方・伝え方|特徴一覧も紹介
就活では、長所は定番の質問です。しかし思いつかなかったり、自分には長所がないと思い込んでいたりする人もおり、何を書けばよいのかわからない方もいるでしょう。まずは自己分析をし、自分にどんな長所があるかを考えてみてください。この記事では、長所一覧と例文を紹介しています。
続きを見る
適応力が求められる理由
社会人として生活するなかで適応力が求められる理由として、次のようなことが考えられます。
環境・状況の変化が激しい時代である
昨今はAIやDXといった、技術の進歩が早い時代です。これにより、働く人間の環境や状況にも変化が伴います。
DXとは
デジタル・トランスフォーメーションの略。デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルなどを変革すること。
また今後も新型コロナウイルス感染症の影響があったときのように、これまで経験したことのない社会全体の変化が起こる可能性があるかもしれません。
従来のやり方が通用しない状況であっても、環境にあわせて自分で考え行動できる、適応力のある人が重宝されるでしょう。
トラブルに対して柔軟に対応する必要がある
業務において、社内外でトラブルが発生することはあるでしょう。そういったとき、瞬時に自分が何をすべきかが判断することで、トラブルを適切に対処できます。
どんな人でも失敗したり、トラブルに巻き込まれたりすることはありますが、その際に「どう対応するか」が重要です。
従来のやり方やマニュアルどおりではなく、状況に応じて対応できる力は、仕事でもプライベートでも役に立つでしょう。
キャリアが多様化している
世の中が変化するにつれ、キャリアの選択肢も多様化しています。学生から新社会人になるための就職だけではなく、転職やキャリアアップ、人によっては副業などにより未経験の分野やキャリアに挑戦する方もいるでしょう。
変化する時代のなかで「将来のために、どんなスキルを身につけなければならないのか」など、自分が成長する手段を柔軟に判断し、よい人生を歩むためにも、適応力の高さは必要です。
適応力が高い人の特徴
適応力が高い人の特徴は次のとおりです。

身近にいる「いつもうまく立ち回りができているな」という人は適応力が高いのかもしれません。ここで紹介するような特徴があるか、振り返ってみましょう。
変化に対して前向きな姿勢である
いつもと違うできごとやトラブルが起こったとき、落ち込んだり文句を言ったりすることがない人は、適応力が高いといえるでしょう。
ネガティブな思考に陥らず、「じゃあどうしようか」と次にやるべきことを前向きに考えるまでのスピードが早いことが特徴です。
よりポジティブな人の場合、変化を「ワクワクする」と捉える人もいるでしょう。
新しいやり方・意見を素直に受け入れる
今までと環境が変化したとき、ネガティブ思考になったり、行動をしたくなくなったりする人もいるでしょう。
適応力が高い人は、そういったときでも「とりあえずやってみる」ことを優先します。考え込むのではなく、行動するなかでよりよい案を生み出そうとする人は、適応力が高いといえるでしょう。
年齢・性別・立場に関係なくコミュニケーションがとれる
学校、職場、趣味などさまざまなシーンで、誰とでも親しくなれる人、コミュニケーションをとれる人は適応力が高いでしょう。
立場や性格、価値観が違う人でも、自然と相手を受け入れ理解しようとする適応力によって、相手と距離を縮めるまでの時間も短くなります。
自分の強み・弱みを客観視できている
自分の強みや弱み、得意不得意を理解しているからこそ、環境にあわせてどんな行動をすべきかを理解していることも、適応力の高さによるものです。
得意なことでは積極的に行動しながら周囲をリードしていき、不得意なことは周囲に相談するなど、自分がやるべきことを理解しています。
感情のコントロールが上手である
例えば仕事でクレームを受けたとき、適応力が高い人は状況を受け入れる能力があるため、感情的に行動をしないでしょう。まずは、何が理由でクレームを受けたのか話を聞いて状況を整理します。
そして、相手と自分どちらが悪いのか、これからどんな行動をして誰に相談しなければならないのかを落ち着いて判断します。
仕事だけではなく、プライベートで知人とのトラブルや不快な出来事があった場合でも、感情のまま相手に言葉をぶつけるようなことはありません。
自分の適応力はどれくらい?適応力診断
ここでは5つの質問にYesまたはNoで答えるだけでわかる、簡易的な適応力診断を紹介します。「自分の適応力はどれくらいなのか」を知るために、チェックしてみましょう。
適応力診断のやり方
- 下の5つの質問にYes・Noで回答
- Yesの数を数える
- Yesの数に応じた点数と、現在の適応力をチェック
■適応力診断
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1.環境が変わっても、わりとすぐに馴染めるほうだ。 | 馴染める:Yes 馴染めるまで時間がかかる:No |
| Q2.初対面の人とでも、あまり緊張せずに話せる。 | 緊張しない:Yes 緊張する・話すのを避ける:No |
| Q3.予定が変わっても、すぐに気持ちを切り替えられる。 | 切り替えられる:Yes 切り替えられない・やる気がなくなる:No |
| Q4.新しいやり方やルールにも、抵抗なくチャレンジできる。 | チャレンジできる:Yes 面倒に感じる:No |
| Q5.忙しくても、うまく優先順位をつけて行動できる。 | 行動できる:Yes 優先順位がわからない・何も考えず行動する:No |
■適応力診断の結果
| Yesの数 | 結果 |
|---|---|
| 0個 | ■変化に慎重な「慎重派タイプ」 ・変化に不安を感じやすい慎重派 ・慎重だからこそ見えることもある ・自分のペースでもよいので、前進を意識したい |
| 1個 | ■変化に対してやや構えがちな「観察型タイプ」 ・状況を把握してから行動したい ・踏み出すきっかけがあれば行動できるタイプ |
| 2個 | ■変化に適応しつつある「成長途中タイプ」 ・状況によってはうまく適応できるタイプ ・自信をもつことができれば、 いろいろなシーンで適応していきやすい |
| 3個 | ■安定して柔軟な「適応タイプ」 ・ある程度どんなシーンでも適応できる ・コミュニケーションや周囲との協力で、 より適応力を高められる |
| 4個 | ■前向きに変化を受け入れる「ポジティブ適応型タイプ」 ・環境の変化に気づきやすく、素早く行動できる ・周囲のサポートまでできるようになれば、 チームのリーダーになれるタイプ |
| 5個 | ■どんな変化も力に変える「高適応力リーダータイプ」 ・すでに適応力が高く周囲を巻き込めるタイプ ・変化を味方にできるポジティブリーダー |
適応力が高くないからといって落ち込む必要はありません。どんな人でも、初めての環境、初めて会う人とのコミュニケーションは、戸惑うことがあるでしょう。
今はまだ適応力が高くない人でも、さまざまな経験を重ねることで「どんなときにどんな行動をすればいいのか」をイメージしやすくなります。

適応力を高める方法が知りたい方は、こちらをチェックしてみてください。
適応力を高めるメリット
適応力を高めることで、次のようなメリットを感じられます。
変化に対するストレスが軽減する
適応力を高めることで、変化に対するストレスを受けにくくなります。
仕事をしていると、自分ではコントロールできない突発的な変化、トラブルが発生することがあるでしょう。適応力が高ければ、「どうすればよいか」を瞬時に判断し行動できるため、ストレスを感じにくくなります。
適応力を上げることで、変化を前向きに捉えられるマインドになり、ストレスよりも「よい刺激」だと捉えられるのです。
人間関係が円滑になる
ビジネスシーンでは、自分とは異なる価値観をもつ人、性格の人と出会い仕事をすることもあるでしょう。適応力があれば「そういう人もいる」と、相手と自分の違いを受け入れやすくなります。
自分とは異なるタイプの人に対して苦手意識を持ちにくくなれば、人間関係も円滑になるはずです。
コミュニケーションがうまくとれれば、協調性も高まり仕事も円滑に進み、仕事でよりよい結果を残せるかもしれません。
頼れる存在になる
適応力が高いと自分が仕事をしやすくなるだけではなく、周囲の人も仕事がしやすくなります。
「あの人は適応力がある」と周知されていれば、業務のなかで起こりがちな、「仕様が変更になった」「急なトラブルが発生した」「新しいジャンルの仕事を依頼したい」といったようなことも相談をしやすくなるはずです。
適応力が高い人は、先輩や後輩などさまざまな人から頼られるでしょう。
成長スピードが高まる
適応力が高い人はさまざまな人から頼られるため、新たな仕事やトラブルに関する相談をされる機会も増え、そのぶん経験が積み重なります。さまざまな経験を重ねることができれば、成長するスピードも高まるでしょう。
同じような仕事だけをしたい人よりも、いろいろなことに対応してきた人のほうが、経験の種類や数が多いぶん成長が期待できます。
キャリアの選択肢が広がる
適応力が高い人は、どんな職場・業界でもやっていけるイメージがつきやすいはずです。また「どんな環境でも活躍できる」という自信がつきます。
さまざまなことに挑戦できるメンタリティをもっていれば、昇進をするために積極的に努力をする、未経験の業界に挑戦してみる、独立するなど、キャリアの選択肢が広がりやすいでしょう。
キャリアの選択肢が広がれば将来的に、本当に自分がやりたいこと、自分にとって幸せな環境も見つかりやすくなることがメリットです。
適応力を高める方法
適応力を高める方法として、次のようなものがあります。

適応力を高めたい方は、自分ができそうなことから取り入れてみましょう!
自ら新たな環境に飛び込んでみる
さまざまな経験を積み重ねるために、あえて自分から新たな環境に飛び込んでいくことも大切です。
例えば、普段は話さない人に声をかける、趣味のサークルに入ってみる、いつもとは違う店で飲食をするといったことです。
今の自分とは違う価値観に触れることで、視野が広がり適応力も身についていくでしょう。
「変化・失敗=成長のチャンス」という思考をもつ癖をつける
変化が起こったときやトラブルが起こったとき、無意識に「嫌だな」「面倒くさいな」と物事を避けようとすることがあるでしょう。そういったときでも、「成長するチャンスかも」と思い込む思考の癖をつける方法があります。
「なぜこんなトラブルが起こったのか」「自分ならトラブルをどう解決するか」など、少し先のことを頭で想像するだけでも、適応力が身につくはずです。
情報収集・学びを継続する
変化に対処していくためには、日々知識、スキルのアップデートが大切です。
仕事での適応力を身につけたいなら、SNSやニュースなどを使い、情報を日々収集していくようにしてみましょう。自分が興味があるジャンル以外の新しいニュースも取り入れることで、知見が広がるでしょう。
小さな変化から取り入れてみる
「適応力を高めたいけど、思い切った行動ができない」という方は、自分の身の回りから新たな挑戦をし、変化を取り入れることもおすすめです。
小さな変化を取り入れる例としては、次のような方法があります。
- 通学・通勤ルートを少しだけ変えてみる
- 普段読まないジャンルの本を読む
- 普段聞かないジャンルの音楽を聞く
- ランチなどでいつものメニューから初めて注文するものにしてみる
- 日常のルーティンに変化を取り入れる など
内容は些細なことであっても、「自ら変化を選んだ」という経験が、変化を起こし受け入れる、適応力の一歩になるかもしれません。
適応力の高さを活かせる仕事
適応力を高めることで、次のような仕事で自分の力を発揮しやすくなるでしょう。
広報・マーケティング
市場やユーザーの移り変わりが早く、それを掴み戦略を柔軟に変えていくのが、広報やマーケティングといった仕事です。常にトレンドを追うことが必要になるため、変化に対応するだけではなく、変化に対して前向きに捉えることが大切です。
広報やマーケティングの場合、社内外の人たちとコミュニケーションをとる機会があると考えられ、さまざまな面で適応力が求められるでしょう。
企画
企画を行う仕事では、世の中の変化に応じた企画を立案していく必要があります。
顧客はもちろん、チームの反応をうかがいながら柔軟に企画を変更、決定していくことになります。物事を0を1にする作業が多い企画では、試行錯誤も多く、柔軟な思考が求められるでしょう。
販売・接客
販売や接客といった仕事では、日々さまざまな顧客と関わります。顧客が変われば、対応や起こるできごとも異なり、それに応じた対応・適応をすることが必要です。
イレギュラーなできごとは発生すれば、状況に応じた適切な対応が求められます。
また、販売する商品やサービスによっては、季節やトレンドといったことで変化もあるので、知識を身につける適応力も必要になるでしょう。
-
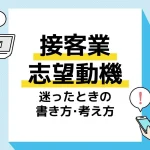
-
【例文8選】接客業の志望動機の書き方|何を書くか迷ったときに考えたいこと
接客業の志望動機を考えるときは、エピソードを深掘りすること、将来のビジョンも伝えることが重要です。「好きだから」という理由だけでは熱意が十分伝わりきらない可能性もあるため、オリジナリティーのある内容を意識してみましょう。
続きを見る
営業
営業職の場合、顧客のニーズにあわせて自社の商品やサービスを提供します。
成果を出すためには、相手が求めていること、対応してくれる人のタイプにあわせて柔軟な提案、コミュニケーションをとることが必要です。そのため、「相手にあわせてどう動くか」を常に考える適応力が求められるでしょう。
-
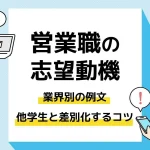
-
営業職の志望動機はこう書く!業界別の例文と他学生と差別化するコツを解説【新卒】
営業職の志望動機では「営業職を選んだ理由」「その企業を志望した理由」を明確に伝えることが大切です。この記事では、志望動機の構成や注意点などを詳しく解説します。業界別の例文とポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
続きを見る
適応力の高さは就活でアピールできる
適応力の高さは、日常や仕事で役立つことのほか、就活で自分の魅力をアピールするときにも使えます。どんなシーンで適応力の高さを発揮し、周囲にどんな影響を与えたのかをエピソードにすることで、自己PRや長所などでアピールできます。
ここまで紹介してきたように、適応力の高さはビジネスシーンで役立つことが多く、自分が成長する機会にもなるでしょう。
適応力の高さを自己PRで伝えるときの例文
ここでは、適応力の高さを自己PRで伝える例文を紹介します。
適応力を自己PRで伝える例
私の強みは、変化に柔軟に対応する「適応力」です。
大学3年生のとき、アルバイト先の店舗が突然リニューアルし業務内容やオペレーションが大きく変更されました。マニュアルが整備されていないなか、私は新しい業務を自ら覚え、後輩スタッフへの共有や改善提案にも取り組みました。
その結果、1カ月後には以前と比較し業務効率が大幅に改善され、店長から「変化を前向きに引っ張る存在」と評価されました。
この経験で培った柔軟性と行動力を活かし、御社のマーケティング部門で、トレンドや市場の変化にも素早く対応しながら、最適な広報戦略を提案・実行できるよう尽力していきたいです。
自己PRのポイント
- 第三者である店長から、適応力の高さをどう評価されたのかを伝えている
- 志望企業、志望部署で適応力の高さをどう活かすかを伝えている
-
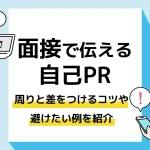
-
面接で伝える自己PRのポイントと例文集!周りと差をつけるコツや避けたい例を紹介
就活の面接における自己PRでは、企業側のニーズを踏まえたうえで、自分の強みや熱意を効果的にアピールすることが重要です。この記事では、面接での自己PRの伝え方・話し方のポイントや回答例、自己PRで避けるべき内容などを詳しく解説します。
続きを見る
よくある質問
適応力を言い換えるとどんな言葉になりますか?
「適応力」は、順応力や柔軟性、臨機応変といった言葉に言い換えることができます。
厳密には意味が異なりますが、いずれも「状況に応じて思考、行動が変えられる力」という意味をもちます。
適応力が高い人の特徴を教えてください
適応力が高い人の特徴は、次のとおりです。
・変化に対して前向きな姿勢である
・新しいやり方・意見を素直に受け入れる
・年齢・性別・立場に関係なくコミュニケーションがとれる
・自分の強み・弱みを客観視できている
・感情のコントロールが上手である
詳細は「適応力が高い人の特徴」で紹介しています。
適応力を高める方法を教えてください
適応力を高める手段としては、次のような方法があります。
・自ら新たな環境に飛び込んでみる
・「変化・失敗=成長のチャンス」という思考をもつ癖をつける
・情報収集・学びを継続する
・小さな変化から取り入れてみる
それぞれの方法を詳しく知りたい方は、「適応力を高める方法」をチェックしてみてください。
適応力を就活でアピールすることはできますか?
適応力は、自身の長所のひとつになりうる要素です。
適応力が高いと、日常生活だけではなく、ビジネスシーンで役立つことがあります。学生生活のなかで自分が適応力の高さを発揮した場面をエピソードにすることで、「長所」や「自己PR」としてアピールできるでしょう。
適応力が高いとどんなメリットがありますか?
適応力を高めることで、次のようなメリットを感じられるでしょう。
・変化に対するストレスが軽減する
・人間関係が円滑になる
・頼れる存在になる
・成長スピードが高まる
・キャリアの選択肢が広がる
詳細は「適応力を高めるメリット」で紹介しています。