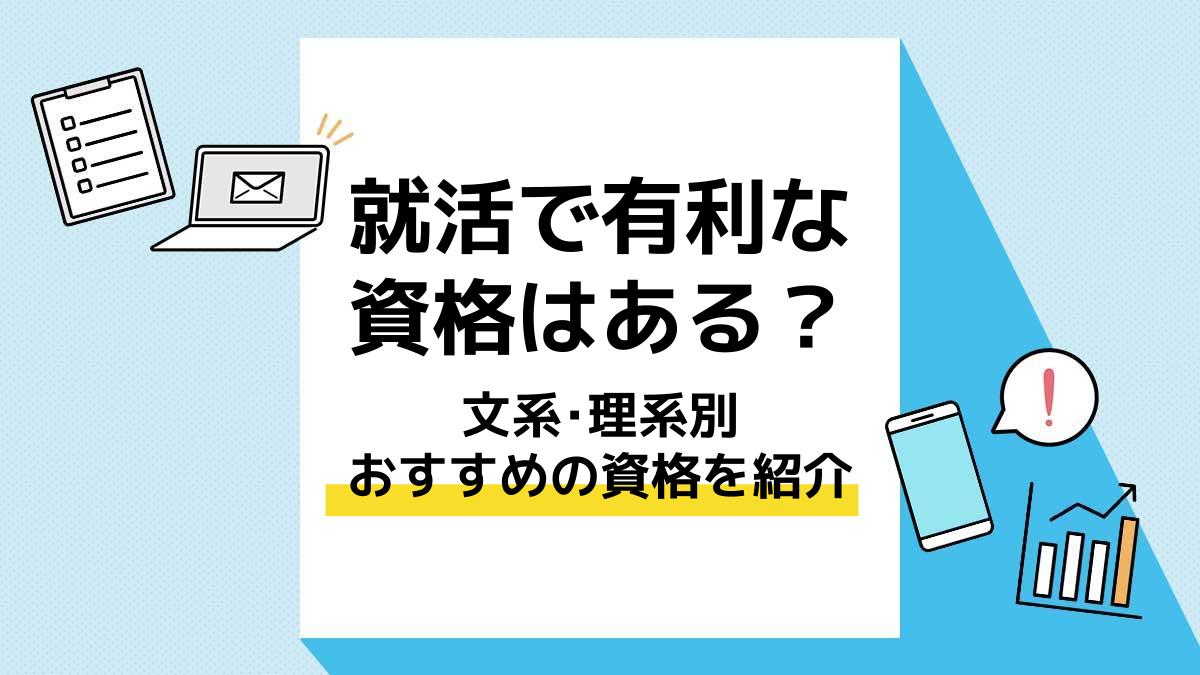就活において、一部の仕事を除いて資格取得は必須ではありません。しかし、自分のスキルをアピールする材料になる可能性はあります。
就活の方向性や目指す業界や企業を考えたうえで、自分にとって必要な資格があれば、勉強をスタートするのもおすすめです。

この記事でおすすめしている資格は、すべてES(エントリーシート)や履歴書に書けるものです。取得している方は記載して、自分のアピールにつなげましょう!
この記事でわかること
- 資格の内容によっては、自分の強みやスキルをアピールする武器になる
- 資格がなくても、ガクチカなどで自分をアピールすることはできる
- 業種によっては、資格以外の経験、スキルのほうが重視されることがある
監修者からのコメント

「就活に有利な資格は何だろう」「今から資格を取れば就活に役立つのか」と気になる人もいるでしょう。新卒の就活は、資格がなくても大丈夫なケースが多いですが、せっかく取得する/取得したものがあるならば上手にアピールしたいものです。この記事で就活におすすめの資格とアピールするときのポイントについて理解を深めてください。
※本記事で紹介する資格は2025年6月時点の情報です
資格はいらない?就活で有利な資格とは
「この資格があれば、志望する企業の選考に突破できる」といった資格は基本的にありません。就活は資格以外にもつスキルや経験、その人の強み、価値観、成長性となどをトータルで見ているからです。
一方で、業務内容に関連する資格であれば、取得していると「ある程度知識がある」と示す材料になるでしょう。
なお、募集要項に「◯◯の資格があると望ましい」や「TOEIC◯点以上」などの記載がある場合は、その内容に沿った資格などを保有しているほうが、有利になる可能性はあります。

勉強する時間、体力が限られますが、働きながら資格を取得するという手段もあります。
仕事によっては資格取得が必須
就活に資格は必須ではありませんが、なかには国家資格などを取得したことを前提に、就活を行う場合があります。
例えば看護師、薬剤師、保育士、管理栄養士などの場合、所定の課程を修了したり試験に合格したりするなどして、資格を取得する前提で就活をします。また、その職業として働くためにも資格が必要となるため、資格が就職に必須です。
そのため、卒業・就職までに資格を取得できなかった場合は、内定に影響が出る可能性がありますので、計画的な準備をおすすめします。
役に立ちそうな資格をもっていないときはどうする?
もうすぐ就活がスタートするのに、自分には役に立ちそうな資格がないから不安です……。


資格が必須の場合を除き、資格がないからといって、就活で不利になるわけではないんです!
資格がなくても、アルバイトやインターン、ゼミ、サークルといった学生時代の経験をもとに、自分をアピールすることができます。学生の本業である学業に取り組んだ成果も、アピールにつながります。
「資格がなくても、今の自分は企業でどんな活躍ができるのか」といったように、働く姿や熱意を伝えることで、自分の魅力を伝えられるでしょう。
【全業界・全職種】就活で役立つおすすめの資格
業界・職種にかかわらず役立つ資格は次のとおりです。
これらの資格は取得が必須ではないですが、資格そのものや学んだ内容が、実務の役に立つ可能性が高いことが特徴です。いずれの資格も難易度が極端に高いものではないため、時間やお金に余裕があるとき、挑戦してみてもよいかもしれません。
TOEIC
TOEICとは、聞く力と読む力に重点を置いた英語コミュニケーション能力を世界共通の基準で評価する試験です。日本でも有名な英語資格のひとつであり、多くの企業に認知されています。TOEICは合格・不合格といった合格基準はなく、取得した点(スコア)であらわすことが特徴です。
就活では「TOEIC◯点以上が望ましい」など、募集要項で記載する企業もあります。外資系企業や商社など、英語力が求められるさまざまな業界、職種の就活で役に立つでしょう。
受験するメリット
- 自分の「英語力」を客観的な視点で証明できる
- 海外市場への進出が活発な企業では、TOEICの資格が有利な要素となる可能性がある
■TOEICの概要
| 受験料 | 7,810円 |
| 合格率 | - |
| 試験の実施 | 年間10回程度 (地域による) |
| 受験資格 | なし |
-
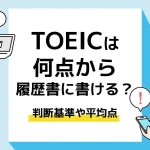
-
TOEICは何点から履歴書に書ける?点数別の判断基準や平均点を紹介【就活】
TOEICには600点以上から履歴書に記載することがおすすめです。ただし、企業や職種によって求められるスコアは異なります。この記事では、履歴書に記載できるTOEICスコアの目安や履歴書への記載方法、平均点などを詳しく解説します。
続きを見る
MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)は、Microsoft Office製品のスキルを証明できる国際資格です。Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlookの5科目から選択して受験でき、随時更新されるバージョンごとの知識が出題されます。
ビジネスシーンで活用するツールがどれくらい利用できるかについて評価されるため、Microsoft Office製品を用いる企業であれば、「Microsoftのツールが使える」と示すことができます。
レベルは「一般レベル」と「上級レベル」の2種類です。
取得するメリット
- ほとんどの企業の業務でパソコンを用いるので、どの企業でも実務に活かしやすい
- Microsoft Office製品を用いる企業の一般事務なら、即戦力になる可能性がある
■MOSの概要
| 受験料 | 一般価格:12,980円 学割価格:9,680円 |
| 合格率 | 非公開 |
| 試験の実施 | 一斉試験:毎月1~2回 随時試験:ほぼ毎日実施(地域による) |
| 受験資格 | なし |
普通自動車第一種運転免許
「普通自動車第一種運転免許」とは、いわゆる自動車免許のことです。
業務で自動車を運転する場合、自動車免許を取得している必要があります。例えば、営業などを行う際、営業車に乗って移動をする業務の場合は免許が必須です。
自動車免許を取得するためには、自動車学校で卒業検定に合格したあと、運転免許試験場で学科試験に合格することで、免許が交付されます。
自動車免許は取得に数カ月かかる場合があるため、社会人と比較して時間をつくりやすい学生のうちに取得しておくのがおすすめです。
取得するメリット
- 業務だけではなくプライベートでも車を運転できる(マイカー・レンタカーなど)
- 学生であれば、自動車学校の料金で学割が適用されることがある
■普通自動車第一種運転免許の概要
| 受験料 | 自動車学校の教習料金:30万円前後 試験手数料:4,000円程度 |
| 合格率 | 73.6% (令和5年・AT限定含む) |
| 試験の実施 | 通年で実施 |
| 受験資格 | 18歳以上 |

自動車学校の料金や試験日、運転免許センターでの手数料や試験日は、都道府県などによって異なります。

多くの業界・職種で資格は必須ではありませんが、「就活で役立つから資格を取る」のではなく、「仕事で役立つだろうから」「試験勉強そのものが面白く、学業の役に立つから」といった理由で資格を取得するのは自分自身にとってプラスになりますし、前向きな印象を与えます。
【文系】就活で役立つおすすめの資格
ここでは、文系の学生におすすめの資格を紹介します。
秘書検定
秘書検定は、ビジネスパーソンとして必要な基本的な常識を習得するための資格です。
「人柄育成」を目指して実施されている検定で、「表情」「態度」「振る舞い」「言葉遣い」「話し方」からわかる「感じのよさ」の表し方について、筆記試験問題と面接試験を通して提唱しています。
秘書検定には、3級、2級、準1級、1級があり、「2級と3級」というように同時に試験を受けることも可能です。試験は筆記試験で、準1級、1級には面接試験もあります。
取得するメリット
- あらゆるビジネス環境で適切な振る舞いを行うための、具体的な手段を学べる
- 社会人の経験がなくても、ビジネスマナーを理解しているとアピールできる
■秘書検定の概要
| 受験料 | 1級:7,800円 準1級:6,500円 2級:5,200円 3級:3,800円 |
| 合格率 | 1級:26.7% 準1級:44.9% ※第134回 2024.11.17受験者状況より 2級:57.2% 3級:59.2%※ 第135回 2025.2.9受検者状況より |
| 試験の実施 | 年2~3回 |
| 受験資格 | なし |
フィナンシャル・プランニング技能検定(FP)
フィナンシャル・プランニング技能士(FP)は、家計にかかわるお金の知識をはじめ、税金、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を証明できる資格です。
取得することで、暮らしとお金に関するアドバイスを行う「ファイナンシャル・プランナー」として活動できます。
フィナンシャル・プランニング技能検定3級は、学生も受験することができます。2級は、3級に合格、実務経験(趣味などは不可)または、AFP認定研修の修了が必要です。まずは3級の取得を目指してみましょう。
取得するメリット
- 保険会社、証券会社、不動産会社、税理士事務所など金融機関での就活に役立つ
- 自分や家族の生活に関連する知識を身につけることができる
■FPの概要
| 受験料 | 3級:8,000円 2級:11,700円 (学科・実技ともに受験する場合) |
| 合格率 | 3級学科:85.4% 3級実技:85.6% ※2024年10月~2025年2月 2級学科:44.4% 2級実技:48.8% ※2025年1月 |
| 試験の実施 | 3級・2級はほぼ毎日 (休止期間を除く) |
| 受験資格 | 3級:なし 2級:あり |
日商簿記検定
日商簿記検定(日本商工会議所および地方商工会議所主催 簿記検定)は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と財政状態を明らかにするスキルを測る試験です。経理事務で必要とされる会計知識や財務諸表を読む力、基本的な経営管理や分析能力を評価します。
日商簿記検定は1級・2級・3級があり、簿記2級以上を求める企業や職種もあります。3級を受けず、2級から受験することも可能です。
簿記には、日系簿記検定以外に「全商簿記検定(全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定)」があります。これは商業科の高校生向けの試験であるため、就活でアピールするなら「日商簿記」の2級以上が望ましいでしょう。
取得するメリット
- 経理担当者だけではなく、事務職、営業職にも役立つ知識を得られる
- 今後、管理職を目指すとき、キャリアアップに役立つ経営の知識も得られる
■日商簿記検定の概要
| 受験料 | 1級:8,800円 2級:5,500円 3級:3,300円 ※事務手数料として別途500円 |
| 合格率 | 1級:15.1%(統一試験・168回) 2級:20.9%(統一試験・169回) 3級:28.7%(統一試験・169回) |
| 試験の実施 | 統一試験:年2~3回 団体試験:企業・学校により異なる ネット試験:試験会場により異なる |
| 受験資格 | なし |

合格率は試験の回によって、10%前後の差が出ることがあります。
日経TEST
日経TESTは、日本経済新聞社と日本経済研究センターが主催している資格試験です。ビジネスに必要な幅広い知識と汎用スキルを評価するために、「経営環境」「企業戦略」「会計」など、複数のビジネス分野から出題されます。
日本経済新聞社が報じるニュースやグローバル経済を題材にした問題が出題されることも特徴です。
個人での受験方法は、全国約100カ所のパソコン教室・専門学校などで受験する「テストセンター試験」と、オンラインで受験する「全国一斉試験」の2種類を選べます。
試験結果はスコアで表示されるため、合格・不合格はありません。
受験するメリット
- 経済、ニュースに対する理解度を客観視できる
- 受験のために勉強をすることで、社会情勢やトレンドに関する洞察力を高めることにつながる
■日経TESTの概要
| 受験料 | テストセンター試験:6,600円 全国一斉試験:6,600円 |
| 合格率 | - |
| 試験の実施 | テストセンター試験:いつでも受験可能 全国一斉試験:原則年1回 (1週間のうち都合のよい日時を選択) |
| 受験資格 | なし |
宅地建物取引士(宅建)
宅地建物取引士(宅建)は、宅地・建物の売買や宅地建物取引業で必要とされる専門知識を証明できる国家資格です。宅建業法、権利関係(民法など)、法令上の制限、税金に関する知識を含む4科目が出題されます。
合格率は約19%で、約5人に1人の割合となりますが、学生は社会人と比べて勉強時間を確保しやすいことから、合格する可能性は十分にあるでしょう。
宅建士になるための試験は誰でも受けることができますが、「宅建士」を名乗り業務を行うには、登録を行う必要があります。一定期間以上実務経験がない場合、登録前に講習を受けなければなりません。
そのため、学生時代に取得後、不動産とは無関係の企業に就職して年月が経過し、既卒で不動産関連企業に勤務する場合は、講習を受けるなどの手順を踏む必要があります。
取得するメリット
- 不動産に関するプロフェッショナルとして認められる
- 「宅建取得者」を応募条件とする求人もあり、不動産業界で働く際の武器となる
■宅地建物取引士の概要
| 受験料 | 8,200円 |
| 合格率 | 18.6% ※令和6年度 |
| 試験の実施 | 年1回 |
| 受験資格 | なし ※資格登録は一定の条件あり |
中小企業診断士
中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に関するアドバイスを行う専門家であり、国家資格です。
試験には、経済学や財務、会計、経営、法務に関連することが出題されます。経済学部など、関連することを学んでいる学生にとっては、資格試験の勉強をすることで学びをより深められるでしょう。
試験は第一次試験、第二次試験と2回あります。第二次試験には「口述試験」と呼ばれる、口頭で回答するものがあります。
第一次試験合格の有効期間は2年間で、第一次試験に合格した年とその翌年に第二次試験を受け、合格をしなければなりません。試験の難易度は高いですが、将来を見越してキャリアアップにもつながる資格といえるでしょう。
なお、二次試験に合格したあと、3年以内に15日間の実務要件を満たすと診断士としての登録申請ができます。
取得するメリット
- 金融業界、コンサルティングといった経済に関連塗る業界の就活で役に立つ可能性がある
- 実務経験を重ねることで、将来的にコンサルタントや経営支援など独立して働くこともできる
■中小企業診断士の概要
| 受験料 | 第一次試験:14,500円 第二次試験:17,800円 |
| 合格率 | 第一次試験:27.5%前後 第二次試験:18.7%前後 ※令和6年度 |
| 試験の実施 | 年1回 |
| 受験資格 | なし |
【理系】就活で役立つおすすめの資格
次に、理系の学生におすすめの資格を紹介します。
ITパスポート
ITパスポートは、基礎的なIT知識全般に関する国家試験です。学生も含め、独学での合格を目指せる試験です。試験時間は120分で、経営全般、IT管理、そしてIT技術に関する知識などが四肢択一式の問題で出題されます。
試験は全国47都道府県の試験会場でCBT方式にて随時実施しています。
CBT方式とは
試験会場に設置されたコンピュータを利用して、オンライン上で受けるテストの方式のこと
取得するメリット
- ITに関する基礎知識は業種・職種を問わず求められるため、文系の学生にもおすすめ
- ITに関連するビジネスの基礎知識も同時に学べる
■ITパスポートの概要
| 受験料 | 7,500円 |
| 合格率 | 大学:50.3% 短大:26.3% 専門学校:20.4% ※令和7年4月時点 |
| 試験の実施 | 随時 |
| 受験資格 | なし |
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験とは、ITエンジニアが基礎を身につけるための資格で、「ITエンジニアの登竜門」といわれています。ITエンジニアとしてキャリアをスタートしたい人が基本情報技術者試験を受け、基礎知識を身につけることで、ITに関連する応用力が広がるでしょう。
情報セキュリティやプログラミング、システム開発、ソフトウェア・ハードウェア設計などの基本が試験内容となっており、ITパスポートよりも専門的な内容であることが特徴です。
ITの分野を学んでいる人はもちろん、将来企業の情報システム部門、社内システムなどで働きたい人にも向いています。
試験は、CBT方式で実施されます。
取得するメリット
- ITに関する専門用語、しくみを理解するのに役立つ
- IT業界を志望する文系の学生が、ITの基礎知識を身につけていることをアピールできる
■基本情報技術者試験の概要
| 受験料 | 7,500円 |
| 合格率 | 40.8% ※令和6年度 |
| 試験の実施 | 随時 |
| 受験資格 | なし |
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験とは、基本情報技術者試験の上級資格で、「ワンランク上のITエンジニア」向けの資格です。ITエンジニアとしてレベルアップをするためには、基本情報技術者試験に合格したあと、応用情報技術者試験に挑戦してみるといいかもしれません。
応用情報技術者試験を受験するための勉強により、技術・管理・経営といった応用力を身につけられるでしょう。
試験は、春期・秋期の年2回、筆記試験で実施されます。応用情報技術者試験は、CBT方式の受験がありません。
取得するメリット
- 応用力のあるITスキルをもっていることをアピールできる
- 応用情報技術者試験に合格していれば、ほかの試験(情報処理技術者試験の高度試験・情報処理安全確保支援し試験)で一部免除になることがある
■応用情報技術者試験の概要
| 受験料 | 7,500円 |
| 合格率 | 23.6% ※令和6年度春期 |
| 試験の実施 | 年2回(春期・秋期) |
| 受験資格 | なし |
危険物取扱者
危険物取扱者とは、化学物質などを安全に取り扱うことができることを証明する国家資格です。危険物取扱者に「甲種、乙種、丙種」といった種類があり、種類に応じて取り扱える危険物が異なります。
資格の種類
- 甲種:すべての危険物の取り扱い・立ち会いが可能
- 乙種:1~6の種類があり、種類によって取り扱える・作業に立ち会える危険物が異なる。例えばガソリンの取り扱いは、「引火性液体」の乙種第4類の資格が必要
- 丙種:引火性液体のみの取扱作業が可能
乙種、丙種は、受験資格はありません。甲種は、理系の学校(大学・高専・短大など)で、科学に関する単位を修得している、または修得し卒業しているなどの要件があります。理系の学校に在学中の方は、単位取得証明書や成績証明書を提出することで受験資格を得られるため、甲種の資格取得を目指してみるのもよいかもしれません。
取得するメリット
- 理系の学生ならではの国家資格を在学中に取得できる
- 化学工場、石油会社、製造業などの就活で役立つ可能性がある
■危険物取扱者の概要
| 受験料 | 甲種:7,200円 乙種:5,300円 丙種:4,200円 |
| 合格率 | 甲種:35.2% 乙種:38.1% 丙種:49.3% 令和6年度 |
| 試験の実施 | 甲種:年6回程度 乙4:月3~4回程度 乙4以外:月1回程度 丙種:月1回程度 ※東京都(中央試験センター)の場合 ※他地域の場合は、試験の頻度が異なります |
| 受験資格 | 甲種:あり 乙種・丙種:なし |
電気工事士
電気工事士とは、店舗などの建物で、電気設備や、配線といった工事を行うことができる国家資格です。
電気工事士には「第一種」と「第二種」があり、その違いは「工事ができる範囲」にあります。第二種は一般家庭や小規模な店舗などの電気工事が対象で、第一種はビルや工場といった大規模な工事にも携わることができる上級資格です。
第二種電気工事士には受験資格はなく、筆記・技能試験に合格することで資格を取得できます。
第一種電気工事士の場合、第二種に合格することに加え、3年以上の実務経験が必要です。そのため学生は、第二種の試験を受け、今後働くなかで実務経験を積みながら、第一種に挑戦してみることを検討してみてください。
取得するメリット
- 第二種には受験資格がなく学生のうちに資格取得をしておけば、将来より専門性が高い第一種電気工事士を目指せる
- どんな時代になっても電気は必須のエネルギーで、電気工事士としての需要がある
■電気工事士の概要
| 受験料 | 第一種:10,900円 第二種:9,300円 ※インターネット申し込み |
| 合格率 | 第一種:61.9%(令和6年下期) 第二種:69.5%(令和6年度) |
| 試験の実施 | 年2回(上期・下期) ※学科試験と技能試験がある |
| 受験資格 | 第一種:あり (第二種に合格+3年以上の実務経験) 第二種:なし |
資格がなくても影響を受けにくい仕事
次の業界や職種は、ここまで紹介したような資格をもっていなくても、活躍できる可能性が高いでしょう。
営業
営業の場合、資格よりもコミュニケーションスキルや人間性を重視すると考えられます。
例えば、傾聴力や提案力、思考の柔軟性、人間関係を構築する力などです。これらのスキルを客観視できる資格はなく、評価の数値化も難しいでしょう。そのため、面接で自分をアピールすることが大切です。
不動産や保険といった専門的な商材の営業であれば、特定の資格があると有利かもしれません。しかしそうではない場合、コミュニケーション能力などのほうが重要だと考えられます。
小売業界
食品や日用品、アパレルなどの小売業界では、資格を必要としないことが多いでしょう。資格や学歴よりも、人柄、経験が重視される傾向があります。
資格ではなく、店舗での成績が昇進などにもつながる業種であり、未経験からでもキャリアアップできる可能性があることが特徴です。
なお、「販売士」のように、接客・販売に関連する資格もあるので、働きながら資格取得を目指すことも可能です。
エンターテインメント業界
映像や音楽、イベント、ゲームといった業界・業種の場合、資格ではなく、創造性やセンス、スキルなどが重視されるでしょう。クリエイティブ職の場合、これまで制作したものをまとめたポートフォリオを見せて、自分の実力を証明することもあります。ポートフォリオの提出は、エントリーをする際に必須となる企業もあります。
志望企業とは関連のない学部で勉強し、趣味や独学で学んでいたとしても、人をひきつけるセンスがある方は、希望した道で就職できるかもしれません。
就活で役立てたい!資格を取得するためのステップ
就活がスタートするまで時間がある場合、資格取得を目指してみるのもよいかもしれません。勉強を始める前に、次のような順番で資格について考えてみましょう。

就活がスタートすると、ES作成や面接練習などにかける時間も必要です。時間に余裕がない場合は、無理に資格を取得する必要はないでしょう。
STEP1. 取りたい資格を探してみる
まずは、将来働きたい業界や職種では、どんな資格が役立ちそうかを調べてみましょう。
趣味で資格を取得するなら自分が好きなものでもかまいませんが、就活で役立てることが前提なら、働きたい業界や業種とマッチすることが大切です。
働きたい業界・業種がイメージできていない場合は、まず自己分析を行い、働いている自分や自分に合う業種などを探してみましょう。

資格の種類を探すときに、過去問などから資格の難易度も確認してみましょう。
-
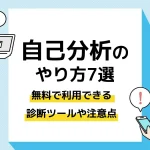
-
自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】
自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
続きを見る
STEP2. 受験資格があるかを確認する
資格によっては、実務経験や、特定の学科で学んでいる、養成学校に通っているといったことが受験に必要となります。受験資格を満たしていないと、勉強をしても受験できません。
実際に資格を取得するためには、受験資格はあるのかも確認することが大切です。
STEP3. 受験日を逆算して計画を立てる
最後に、受験日を調べゴールを決めておきましょう。
資格によって、試験を実施する頻度は異なります。年1回と限られている試験もあれば、1カ月1回など高頻度で実施しているものもあります。
資格勉強をするにあたり、「合格までに合計何時間くらいの勉強が必要か」も調べてみます。そして、1日何時間資格取得のために時間を割けるかを考え、受験日に間に合うよう勉強できるかも逆算しておきましょう。
そうすることで、資格取得が現実的なものであるかを判断できます。

資格取得も大切ですが、就活や学業、人によってはアルバイト、サークル、ゼミなど行っているはずです。体力的・精神的に、無理のない範囲で資格取得を目指してみましょう。
就活で資格をアピールするときのポイント
就活で資格をアピールするときは、次のポイントを意識してみましょう。
資格を取得した動機・過程を伝える
ただ資格を取得したという事実だけではなく、その理由や動機・過程を伝えることで、意欲や価値観、仕事に対する姿勢をアピールできます。
試験に向けた準備、困難に立ち向かった経験、資格取得のための工夫は、自己管理能力や問題解決能力、忍耐力、計画性などをアピールできるでしょう。
学生自身が何に興味を持ち、どんなきっかけで行動を移し努力したのかは、採用する企業側にとっても重要な情報です。
多くの学生が同じ資格を持っていても、資格取得に至るプロセスは一人ひとり異なります。プロセスをアピールすることで、オリジナリティを際立たせることができるでしょう。
業務で資格を活かせるシーンを伝える
企業によっては「取得した資格が具体的に仕事にどんな価値をもたらすか」を知りたいと考えている場合があります。
資格を具体的にどう仕事に活かせるかを示し、業務への応用方法を説明することも重要です。これにより、即戦力として活躍できることをアピールできます。
業務に必須ではない資格については、活かせるシーンを明確に伝えることが大切です。資格と業務に関連性がない場合は、取得を目指したきっかけを伝えられないと、面接官に「何のために取得したのか」と疑問が残るかもしれません。
ES・履歴書には正式名称で記載する
資格によっては、正式名称が長いものもあります。そのような場合でも略すことなく、ES(エントリーシート)や履歴書には、正式名称で記載しましょう。
■資格の書き方例
| 誤った書き方 | 正しい書き方 |
|---|---|
| FP3級 合格 | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 合格 |
| 自動車免許 取得 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
| TOEIC750点 | TOEIC® Listening & Reading Test 750点取得 |
未取得の資格・嘘は記載しない
取得できていない資格や、嘘は記載しないようにしましょう。
選考段階や内定承諾書を提出する際に、取得後にもらえる証明書などを提出することもあるため、取得しているかどうかは企業が把握できます。資格に限らず、すべて真実のみを記載することが大切です。
看護師や管理栄養士などのように、学校の修了が資格取得の条件となっている場合、在学中であっても履歴書に記載することは可能です。このような場合は「取得見込み」と明記しておくことで、採用担当者にも状況が正しく伝わるでしょう。

学習中で、まだ試験を受ける予定がないにもかかわらず、取得済みのように記載するのは誤解を招くためおすすめできません。
就活に影響を与えない資格は記載しない
取得している資格をすべて資格欄に記載する必要はありません。
例えば、小中学生をメインとした難易度が低い資格や、志望企業と明らかにミスマッチの資格、すでに廃止されている資格などは記載しなくても問題ありません。
面接で資格取得に力を注いだことをアピールするときの例文
ここでは、電気工事士の資格を取得するため尽力したことをガクチカにした例文を紹介します。
ガクチカの例文
私が学生時代に最も力を入れたのは、第二種電気工事士の資格取得です。
将来、電気に関わる技術職に就きたいと考え、学業と並行して半年間の独学で合格を目指しました。筆記試験では電気理論や配線図、法令などの幅広い分野を体系的に学び、毎日1時間以上と勉強を積み重ねました。特に苦手だった複雑な配線図では、教科書だけでなくYouTubeの動画も活用して理解を深めました。
また実技試験では、施工条件を理解したうえで正確な配線を行う必要があるため、ミスの原因を記録しながら何度も練習しました。その結果、一発合格を果たすことができました。
この経験を通じて、計画的に努力する力と課題を分析し改善する力を身につけることができました。学んで得た知識と実務経験は、貴社の業務でも活かせると考えています。
ポイント
- 「将来、電気に関わる技術職に就きたいと考え」→ただ資格を取得しただけではなく、将来を考慮し自発的に行動したことを伝えている
- 「課題を分析し改善する力」→資格取得を通して、社会人として働くなかで必要な能力を身につけられたことを伝えている
よくある質問
就活で有利になるおすすめの資格はありますか?
次の資格は、業界・職種を問わずおすすめです。
・TOEIC
・MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
・普通自動車第一種運転免許
TOEICは資格ではありませんが、600〜700点であればビジネスシーンで役立つ可能性があります。
「就活で資格はいらない」というのは本当ですか?
「就活で資格はいらない」と言い切ることはできませんが、「資格がなくても問題ない」という考え方もできます。
資格がない場合でも、就活で自分の魅力を伝え、自分がどんな活躍をするのかをアピールすることで、選考を突破することは可能です。
なお、一部の職業では資格必須で、その場合は卒業までに単位の取得、資格の取得を行う必要があります。
資格はいつまでに取得すれば、就活で役立てることができますか?
資格は、就活がスタートするまでに取得しておくのがおすすめです。その理由として、就活がはじまると資格取得の勉強に時間を割くことが難しくなること、エントリーする際に取得した資格を記載する必要があるためです。
ESや履歴書には、取得していない資格については記載することはできません。そのため、取得した状態で就活に臨むようにしましょう。
監修者情報

監修者:遠藤 美穂子さん
新卒で東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)入行、営業店・本部にて法人営業に携わるほか、新人研修講師、採用面接官も経験。
現在はキャリアコンサルタントとして大学での就活支援、キャリア系講義、社会人向けのビジネスマナーやキャリア開発研修などを行っている。
資格:国家資格キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士