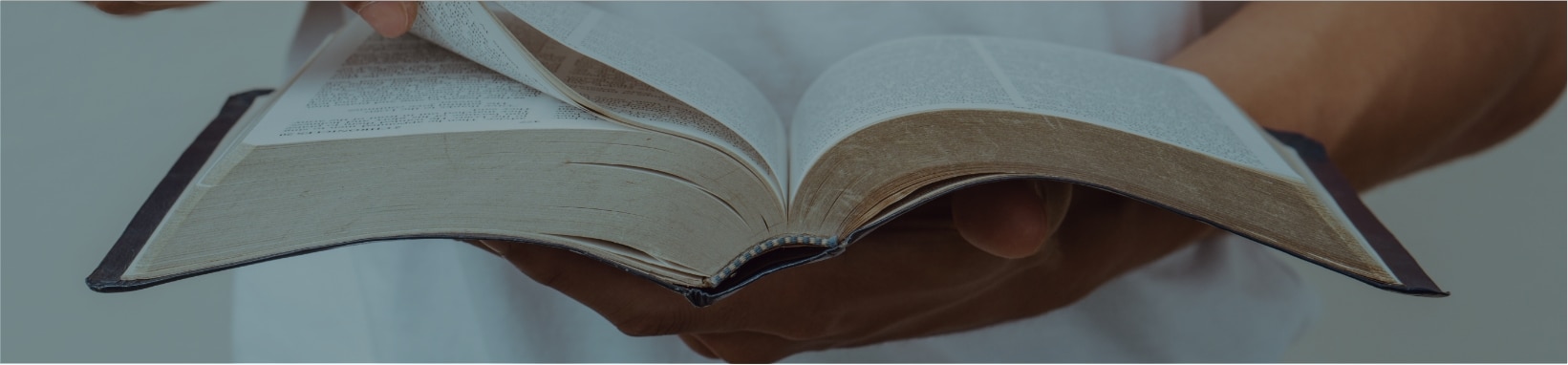法事のときの適切な服装とは?基本のマナーから家族のみの場合についても解説
2025.07.15

この記事の所要時間:約11分
お葬式は喪服と決まっていますが、法事って何を着ればいいか悩みますよね。
法事の種類や参列する立場などによっても服装マナーが異なります。
故人や遺族に追悼の意を示すためにも、正しい法事の意味とマナーを知り、礼節をもって出席しましょう。
※ここでは一般的な法事のマナーや服装についてご紹介します。一部地域や宗派によって異なる場合がございますので予めご了承ください。
1. そもそも法事の意味とは?

法事とは、亡くなった方の冥福を祈って供養する仏教儀式のことです。
遺族は故人が極楽浄土で往生できるよう感謝の気持ちを込めて追善供養(ついぜんくよう)をおこない、四十九日、百箇日、翌年は一周忌と続いていき、三十三回忌で弔い上げといわれ終了になります。
また法事には、遺族が悲しみから立ち直り心を整理するグリーフケアの役割もあります。服装や持ち物は法事の回忌や参列する立場などによって変わるため、特に喪服の種類については事前に確認しておくと安心です。
2. 法要との違い

法事のなかで僧侶にお経を唱えてもらう追善供養を法要と呼びます。一方、法事は、法要や食事会などを含めた一連の行事を指します。
法要には、亡くなった日を起点に初七日から七七日まで全7回おこなう忌日法要と、数え三回忌から三十三回忌までにおこなう年忌法要の2種類があります。お寺や自宅でお経を唱えてもらったあと、お斎の席(食事会)を設けるのが一般的です。
3. 喪服の種類

ひとくちに「喪服」といっても格式があり、以下の3種類に区分されます。
3-1. 正喪服
文字通り正しい喪服という意味があり、最も格式の高い喪服です。
喪主や親族など葬儀の主催側が着用します。
しかし、和装やモーニングを持っている方は少なくなってきていることや葬儀の簡略化も進み、正喪服を着用している方は少なくなってきています。
最近では、喪主や親族など招く立場の方も、準喪服を着るのが一般的です。
3-2. 準喪服
最も一般的な「喪服」とは準喪服のことです。
男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルとも呼ばれます。
四十九日や1回忌~3回忌までの法事に参加する全員が準喪服を着るのが一般的です。
3-3. 略喪服
準喪服より格が下がる略礼服とは「平服」のことです。
「平服でお越しください」と案内がある場合は、略喪服を着用しましょう。
4. 法事の種類に応じて服装は異なる?

法事の種類や故人との関係などに応じて、参列時の服装は異なります。礼節に沿った正しい服装で臨みましょう。
4-1. お通夜・告別式
お通夜とは、家族・親族・知人・友人など、故人と親しい方たちが集まりお見送りのときを過ごす儀式のことです。故人が亡くなった翌日の夕方から夜にかけておこなわれます。
一方、お通夜の翌日の日中におこなわれる儀式を告別式と呼びます。
お通夜や告別式では、家族・親族側は正喪服・準喪服を着用するのが一般的です。それ以外の参列者は、準喪服・略喪服を着用します。
すべての法事に当てはまりますが、カジュアルな服装や肌の露出、光沢のある華やかな装飾品などはマナーとして控えましょう。
4-2. 初七日
初七日とは、死後7日目におこなう法要のことです。故人の魂が三途の川を渡り極楽浄土へ行けるよう、成仏を願う意味があります。
参列者の負担にならないよう、初七日は葬儀の日にあわせておこなわれるのが一般的です。家族は正喪服・準喪服、それ以外の参列者は準喪服での参列となります。
4-3. 四十九日
四十九日とは、死後49日目におこなう法要のことです。
忌明け(きあけ)とも呼ばれ、遺族が故人の冥福を祈り喪に服す期間を終えることをいいます。
葬儀でお世話になった親族、故人の友人や仕事関係の方を招き、お寺や自宅で僧侶にお経を上げてもらい会食するのが一般的です。
遺族や親族は喪服を着用します。
出席者についても、四十九日は葬式同様に喪服を着用するのが好ましいです。
4-4. 百箇日
百箇日とは、死後100日目におこなう法要のことです。
卒哭忌(そっこくき)とも呼ばれ、故人が亡くなって3ヵ月以上経つので、泣いて悲しむのを卒業するという意味があります。
百箇日法要は四十九日後すぐの追悼法要ということもあり、近年では省略することも多く、おこなうにしても遺族や親族のみでささやかに自宅の仏壇で供養します。
服装は四十九日と同様に喪服が好ましいですが、近親者のみでおこなう場合は簡略にして平服でもよいでしょう。
4-5. 一回忌~三回忌
一回忌(一周忌)とは故人が亡くなってから満1年、三回忌(三周忌)とはその翌年の満2年の命日におこなう法要のことです。
三回忌までの年忌法要は四十九日に次いで大切な法要なので、遺族や親族の他に親しかった友人知人を招き、お寺や自宅で僧侶にお経を上げてもらい会食をするのが一般的です。
遺族や親族は喪服を着用します。
出席者についても、三回忌までは喪服を着用するのがマナーになります。
「平服でお越しください」と記載があった場合は案内に従ってください。
4-6. 七回忌~三十三回忌
命日から節目になる年ごとに遺族や親族のみで法要をおこないます。
七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三忌、二十七回忌と続き、年忌法要の最後として三十三回忌で弔い上げになり終了です。
回を重ねるごとに喪の雰囲気は薄れ規模も縮小していくため服装は、喪服から簡略化され平服でよいとされます。
5. 「喪服」で法事に出席するときのマナーについて
故人を偲ぶ場として喪服を着用する際は、マナーに沿った着こなしを心がけましょう。華美な服装をしていては弔意を表すことはできません。
ここでは、喪服のマナーを男女別に分けて解説します。
5-1. 男性の場合

● 喪服
ブラックスーツ(ブラックフォーマル)が好ましい。生地はブラックで光沢素材でないもの。上着はシングル・ダブルどちらでも構いませんが、パンツは裾がシングルのものを着用します。
● シャツ
白無地のレギュラーカラー。色柄物やボタンダウンのシャツは避けましょう。
● ネクタイ
黒無地で、光沢素材でないもの。結ぶ際は、お悔やみの場でのマナーとしてくぼみ(ディンプル)を作らないこと。
● ベルト
黒無地でシンプルなデザインのもの。大きく目立つバックルやクロコやヘビ柄などのデザインはNGです。
● シューズ
ブラックの革靴。原則、紐で結ぶタイプのものでないといけません。エナメルやスエード素材はNG。金具なしのシンプルなものが好ましい。
● 靴下
ブラックの無地。ホワイトや柄物は避けましょう。
● カバン
男性は荷物をポケットに入れてバッグは持たずに手ぶらが一般的です。バッグを持つ場合は、ブラックで金具など装飾のないシンプルなデザインのものにしましょう。
5-2. 女性の場合

● 喪服
ブラックフォーマルが好ましい。ワンピースやアンサンブル、パンツのスタイルが基本です。露出の高いデザインは避け、トップスの袖丈は長袖から5分袖、スカート丈は膝からふくらはぎ丈が上品に見えます。
● アクセサリー
ネックレスやイヤリングは真珠が定番。連が重なるものは「不幸が重なる」とされるため控えましょう。
● バッグ
ブラックの布製が基本で、光沢や飾りのないシンプルなものが好ましい。数珠や袱紗が入る大きさがよい。荷物の多い場合は、ブラックのサブバックを持ちましょう。
● 手袋
ネイルをしている方向けや、露出を控えるためのアイテムとして有効。お焼香の際は外しましょう。
● ストッキング
ブラックの薄手のストッキングが正式。30デニール以下が基本になります。厚手、柄物、網タイツなど華美なものはNGです。
● パンプス
シンプルなブラックのパンプスで、素材は布または革が好ましい。高いヒールのものやエナメル素材、素足の見えるミュールやサンダルはNGです。
5-3. 子どもの場合
子どもの場合、正式な礼装である制服(学生服)を着用するのが一般的です。制服がない場合は、ホワイトのシャツにブラックやネイビーのブレザーとボトムスを着用しましょう。靴下はブラック・ネイビー・ホワイトなどのベーシックカラー、シューズはローファーかスニーカーが好ましいです。
乳幼児は、ダークカラーのシンプルな服装であれば問題ありません。たとえ家族のみの法事であっても、柄物やキャラクターものはマナーとして控えましょう。
6. 「平服」で法事に出席するときのマナーについて

喪の雰囲気は、亡くなってから年数を経るほど徐々に薄くなっていきます。
遺族の気持ちも落ち着き、故人の死を受け入れることができるようになり、いつまでも喪に服すより新たな日常を生きていこうという意味から、七回忌以降は平服で法要をおこなうのが一般的です
6-1. 平服とは普段着ではない
「平服」って言葉、なかなか聞きなれないですよね。
平服を辞書で引くと「日常の衣服、普段着」という意味です。
しかし、法事の場にいつもと同じ格好で出席すると恥ずかしい思いをすることになりますので注意しましょう。
「平服でお越しください」とは、「堅苦しくなく、かしこまった場で着用しても恥ずかしくない服装」のことを指します。つまり平服とは「略礼装」のことです。
平服と言われたからといって、Tシャツにジーンズのようなラフな服装、「カジュアルでOK」と思ったら大きな勘違いになるので、気をつけてくださいね。
6-2. <男女・子ども別>平服の着こなし
厳かな場にふさわしいきちんとした服装が求められます。
ブラック・ネイビー・グレーなどのダークカラーの無地の服装を選ぶのがポイントです。
男性はスーツ、女性はワンピースやセットアップの着用がマナーになります。
詳しくは下記で解説していきます。
6-2-1. 男性の場合

● スーツ
ブラック・ネイビー・グレーなどのダークスーツを着用しましょう。柄はできれば無地がよいですが、織柄や薄っすらとしたストライプまでならOK。
● シャツ
白無地のレギュラーカラー。色柄物やボタンダウンのシャツは避けましょう。
● ネクタイ
ブラックを選ぶのが無難。スーツ同様に控えめな色や柄であれば問題ありません。結ぶ際は、お悔やみの場でのマナーとしてくぼみ(ディンプル)を作らないこと。
● ベルト
黒無地でシンプルなデザインのもの。大きく目立つバックルやクロコやヘビ柄などのデザインはNGです。
● シューズ
ブラックの革靴。原則、紐で結ぶタイプのものでないといけません。エナメルやスエード素材はNG。金具なしのシンプルなものが好ましい。
● 靴下
ブラックの無地。ホワイトや柄物は避けましょう。
● カバン
男性は荷物をポケットに入れてバッグは持たずに手ぶらが一般的です。バッグを持つ場合は、ブラックで金具など装飾のないシンプルなデザインのものにしましょう。
6-2-2. 女性の場合

● ワンピース・セットアップスーツ
ブラック・ネイビー・グレーなどダークカラーのワンピースやセットアップスーツ、アンサンブルが基本。露出の高いデザインは避け、スカート丈は膝からふくらはぎ丈が上品に見えます。小さいお子様がいる方や料理の配膳など動き回る場合は、パンツスタイルでもOK。中に着るトップスもダークカラーで統一してください。ホワイトなど明るい色はNGです。
● アクセサリー
ネックレスやイヤリングは真珠が定番。連が重なるものや大きいものは華やかな印象になるため控えましょう。
● バッグ
ブラックの布製が基本で、光沢や飾りのないシンプルなものが好ましい。数珠や袱紗が入る大きさがよい。荷物の多い場合は、ブラックのサブバックを持ちましょう。
● ストッキング
ブラックの薄手のストッキングが正式。30デニール以下が基本になります。ベージュ、厚手、柄物、網タイツなどは控えましょう。
● パンプス
シンプルなブラックのパンプスで、素材は布または革が好ましい。高いヒールのものやエナメル素材、素足の見えるミュールやサンダルはNGです。
6-2-3. 子どもの場合

学生の場合は、学校の制服を着用しましょう。
学校によっては、「制服の色が明るい」「パンツやスカートがチェック柄」などブラック以外の場合もありますが、学生服が正装とされているので問題ありません。
子どもの場合は、シンプルなデザインの服を選んでください。
ホワイトのシャツにブラックやグレーのズボンやスカートでまとめると好ましいです。
キャラクター等の絵柄が入っているものはNG。
乳幼児もできるだけ飾りのない控えめな服を着せるようにしましょう。
7. 家族のみの法事でも服装マナーは同じ
家族のみの法事であっても、服装マナーは同じです。親族や知人を招くときと同じように、家族のみの法事でも喪服を着用しましょう。
ただし、故人の意向により法要をせず、家族だけで食事会を開く場合もあります。そのような場合は、参列する家族とよく話し合って、喪服にするか私服にするかを検討しましょう。
8. 法事に参列する際の持ち物

法事に参列する際は、数珠・供物・御供物料などを持参します。
供物とは祭壇に飾るもので、フルーツやお菓子、高級焼香や生花などが一般的です。
供物を持参しない場合は、御供物料を持参しましょう。お通夜や告別式の際に持参するお金は香典と呼ばれますが、それ以外の法事で持参するお金を御供物料と呼びます。金額の目安は故人との関係性や立場などによって変わりますが、香典の5〜7割ほど包むのが一般的です。
9. 御供物料に関するマナー
御供物料を包む封筒(不祝儀袋)は、中に入れる金額に合うグレードのものを選びましょう。5,000円以下の場合は水引がプリントされているもの、3万円以上の場合は高級な封筒が好まれます。
封筒にお金を入れる際は、顔を伏せる意味を込めて、お札の表面が封筒の裏面に来るように包むのがマナーです。新札や汚れがあるお札は避け、法事が始まる前に施主に手渡しましょう。
10. まとめ

いかがでしたか?
法事の服装といっても、法要の種類やタイミングによって適切なものは大きく異なります。
四十九日から三回忌までは喪服、七回忌以降は平服を着用するのがマナーです。
前もって予定がわかっている分、事前準備をしっかりとおこない、故人や遺族の方に対する敬意を忘れずに失礼のない服装を心がけましょう。