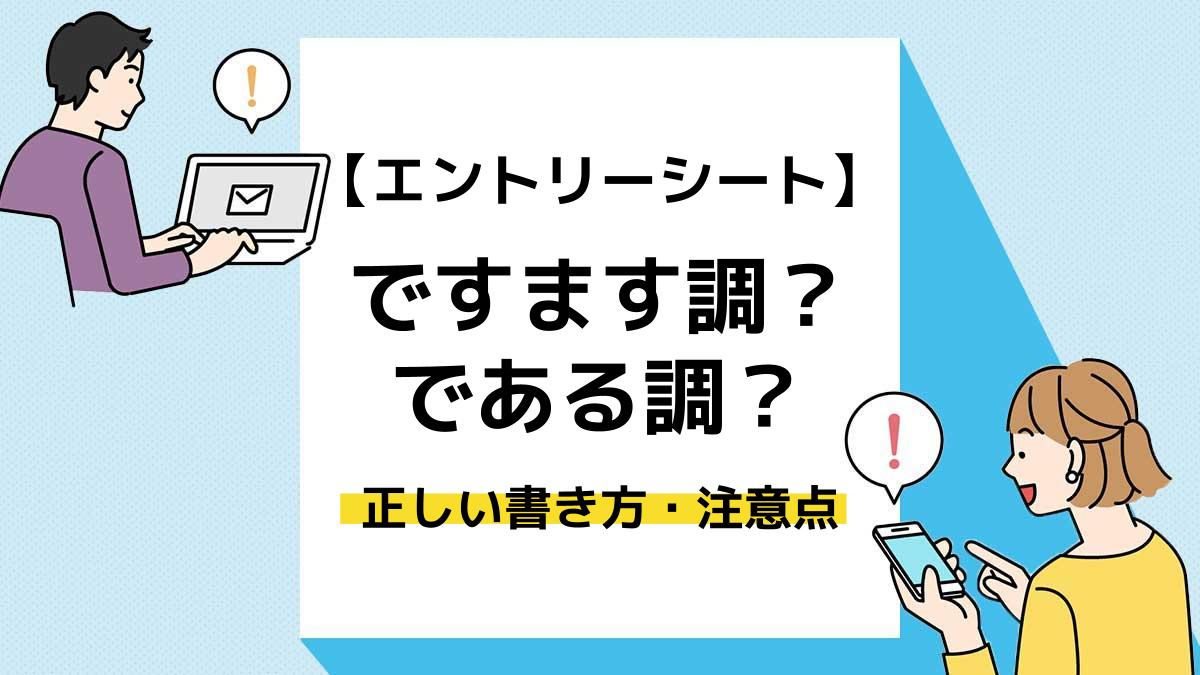文末表現にはおもに「ですます調」と「である調」の2種類があります。エントリーシート(ES)ではどちらの文体を使うのがよいのか迷った場合は「ですます調」で作成するのがおすすめです。
「ですます調」は丁寧な印象を与え、「である調」は説得力を強調するという特徴があります。業界や企業によって、文体を使い分けることも大切です。
それぞれの文体の正しい使い方や注意点を確認して、自分を効果的にアピールするエントリーシートを作成してみましょう。
この記事でわかること
- エントリーシートの文体に迷ったら「ですます調」がおすすめ
- 文体によって相手に与える印象が異なる
- 業界や企業に応じて使い分けることが大切である
エントリーシートは「ですます調」「である調」のどちらでもOK!
エントリーシート(ES)の文体には「ですます調」と「である調」の2種類があり、どちらを使うかは基本的に自由です。企業側から明確な指定がある場合は、そちらにあわせましょう。
それぞれの文体が与える印象には違いがあります。「ですます調」は、丁寧で柔らかい印象があり、親しみやすさや礼儀正しさを感じる文体です。一方「である調」は、論理的で力強い印象を与え、自信や説得力が強調されます。
また、業界や企業の文化などによって、好まれる文体が異なる場合もあります。志望先の特徴を考慮して、文体を選ぶのがおすすめです。
文末を統一することが大切!
エントリーシートの文章で大切なのは、文末を統一することです。「ですます調」と「である調」が混在していると、文章が読みにくくなり、読み手に違和感を与える可能性があります。次の例文で確認してみましょう。
文体が混在した例文
私は学生時代にサークル活動に力を入れました。リーダーとして経験を積んだ。
例文は、前半が「ですます調」、後半が「である調」で書かれています。このように、文体が混在すると読みにくさや違和感が出るため、文体を統一することが大切です。
文体に迷ったら丁寧さと柔らかさが伝わる「ですます」に統一しよう
「ですます調」と「である調」どちらを選ぶか迷う場合は、「ですます調」を使うのがおすすめです。「ですます調」は丁寧で柔らかい印象を与えるため、初対面の採用担当者に礼儀正しさや誠実さを伝えるのに適しています。
特に、接客業やサービス業など、コミュニケーションが特に重視される業界では、「ですます調」が好まれる傾向です。
また、「ですます調」は日常的に使われている文体であるため、普段文章を書く機会がすくない方でも自然な文章を作成しやすいといえます。
ですます調のメリット
「ですます調」でエントリーシートを作成するメリットは、次のとおりです。
丁寧で柔らかい印象を与える
「ですます調」は日常で使われる文体であり、丁寧で親しみやすい印象を与えます。加えて、礼儀正しさや真面目さが伝わりやすいのも「ですます調」のメリットです。
初対面の採用担当者に対して丁寧な表現を使用することで、好印象になることもあるでしょう。
読みやすく、伝わりやすい
「ですます調」は、日常の会話やビジネス文書などでも一般的に使われているため、読み手にとって自然で読みやすい文体です。
採用担当者は多くの学生のエントリーシートを読みます。内容が明確で理解しやすい文章であることも、自分をアピールするうえで大切です。
文章が堅苦しくならず、伝えたい意図が素直に伝わるため、読み手の理解や共感が得やすいことも「ですます調」のメリットです。
一緒に働くイメージを持ってもらいやすい
「ですます調」は話し言葉に近く、実際の職場でのコミュニケーションに近い文体であるため、採用担当者が学生と一緒に働くイメージを持ちやすくなるでしょう。
「ですます調」は、相手に安心感を与えるとともに、協調性やコミュニケーションの円滑さを示せます。採用担当者が「この人と一緒に働きたい」と感じるようなエントリーシートを作成することも大切です。
特に人と関わる業界やチームワークが必要な職種は、親しみやすさが伝わる「ですます調」を使用するのが有効です。
ですます調のデメリット
ですます調には、メリットがある一方で次のようなデメリットもあります。
同じ文末が続くことで文章が単調になりやすい
「ですます調」は読みやすい一方で、同じ語尾が続きがちです。文章全体が単調に感じるため、内容が記憶に残りにくい可能性があります。
体言止めや接続詞を活用して文末に変化をつけたり、過去形を用いたりするなどして、文章のリズムを調整することが大切です。
文字数が増えやすい
「ですます調」は丁寧な表現になりますが、「である調」と同じ内容でも文字数が多くなる傾向があります。文字制限のあるエントリーシートでは、要点を簡潔にまとめることが大切です。丁寧な表現にすると文字数が増えてまとまりにくくなる可能性があります。
文字数の違いを確認してみましょう。
「ですます調」の場合
私の強みは、分析力と問題解決能力です。大学ではマーケティングのゼミに所属し、企業の課題解決に向けた提案を行ってまいりました。入社後も、この経験を活かして戦略立案に携わっていきたいと考えております。(98文字)
「である調」の場合
私の強みは、分析力と問題解決能力だ。大学ではマーケティングのゼミに所属し、企業の課題解決に向けた提案を行った。入社後も、この経験を活かして戦略立案に携わっていきたいと考えている。(89文字)
重要なポイントに絞って記述し、冗長な表現を避けたり、簡潔な表現を活用したりするなど、文字数の調整が必要です。
である調のメリット
「である調」のメリットは次のとおりです。
文章を端的にまとめやすい
「である調」は文末が短く、文章を簡潔にまとめられます。「ですます調」と比較すると、同じ内容でも文字数を抑え、限られた文字数内で多くの情報を伝えられるのがメリットです。
論文や報告書など、情報を正確に伝えることが大切な書類では、端的に内容が理解できるように「である調」が使われていることもあります。
要点を理解しやすいことから、読み手の負担を軽減できる点もメリットとして挙げられるでしょう。
自信と説得力を強調できる
「である調」は断定的な印象が強いため、自己PRや志望動機に使用すると、自信や説得力を強調できます。ビジネス文書や報告書などで「である調」が使われていることが多いのは、堅実さや客観性を強調するためといえるでしょう。専門的な内容や、論理的な解説の信頼性を高めるのにも有効です。
特に、コンサルティング業界やマスコミ業界、商社など、自立性や論理的思考が必要な業界では「である調」が好まれることも考えられます。
である調のデメリット
「である調」のデメリットは次のとおりです。
断定的な表現で、敬意や丁寧さが伝わりにくい
「である調」は丁寧さが感じられにくいため、企業や採用担当者に対する敬意や礼儀正しさが伝わりにくくなることもあります。断定的な表現が特徴であり、目上の人や年長者など読み手によっては高圧的な印象を与えるかもしれません。
特に、接客業やサービス業など、丁寧な対応が重要な職種では、不適切とされる可能性もあります。
「である調」でエントリーシートを書いた場合は「読み手にどんな印象を与えるか」という視点で見直してみましょう。

友人や先生など、第三者に読んでもらい、高圧的な印象になっていないか確認してもらうのもおすすめです。
文章が堅苦しく感じられやすい
「である調」は口語ではあまり使用されないため、読み手が読み慣れていない可能性もあります。文章全体が堅苦しく、親しみやすさに欠ける可能性があります。
そういった文章は、「読みにくい」「内容がわかりにくい」という印象になりがちです。読み手にどんな印象を与えるかを客観的に確認して、エントリーシートを作成してみましょう。
【参考】ですます・であるを使用した例文を比較しよう
エントリーシートを作成する際、「ですます調」と「である調」のどちらを使用するか迷うこともあるでしょう。それぞれ異なる印象を与えるため、エントリーシートの内容や伝えたいメッセージによって適切なほうを選ぶのがおすすめです。
それぞれの文体で作成した志望動機と自己PRの例文を紹介します。どんな印象の違いがあるのか、確認してみましょう。
志望動機
「ですます調」の例文
私は、貴社の「人と人をつなぐ」理念に共感し、志望いたしました。大学時代、地域のボランティア活動に参加し、人々のつながりの大切さを実感しました。この経験を活かし、貴社で多くの人々の架け橋となる仕事に携わりたいと考えております。
「である調」の例文
私は、貴社の「人と人をつなぐ」理念に共感し、志望した。大学時代、地域のボランティア活動に参加し、人々のつながりの大切さを実感した。この経験を活かし、貴社で多くの人々の架け橋となる仕事に携わりたいと考えている。
自己PR
「ですます調」の例文
私は目標達成のために、地道な努力を続けることができます。大学では英語の習得に力を入れ、毎日2時間勉強しました。結果、英語でのプレゼンテーションで教授から高評価をいただきました。貴社でも、継続力を活かして着実に成果を出していきたいと考えております。
「である調」の例文
私は目標達成のために、地道な努力を続けることができる。大学では英語の習得に力を入れ、毎日2時間勉強した。結果、英語のプレゼンテーションで教授から高評価をいただいた。貴社において、継続力を活かし、着実に成果を出したいと考えている。
-
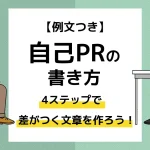
-
【例文つき】自己PRの書き方|4ステップで差がつく文章を作ろう!
自己PRでは、企業が求める人物像を把握したうえで「その強みを企業でどう活かせるか」まで伝えることが重要です。この記事では、自己PRの考え方と書き方を詳しく解説します。アピールポイント別の例文も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
続きを見る
エントリーシートを書くときの注意点とポイント
エントリーシートを作成する際は、次の点を意識してみましょう。
語尾が単調にならないように工夫をする
同じ語尾が続くと文章が単調に感じ、内容が伝わりにくくなる可能性があります。接続詞の活用や、文末表現のバリエーションを増やすなど、文章に変化をつけるように意識してみましょう。
対策例
- 「~しております」「~いたしました」など表現を使い分ける
- 「~でした」「~です」などの時間軸を意識した表現を使う
敬語表現に注意する
敬語には尊敬語や謙譲語、丁寧語の3種類があります。それぞれシーンに応じた敬語の使い分けが大切です。
誤った敬語表現はネガティブな印象を与える可能性があるため、正確な敬語を心がけてエントリーシートを作成してみてください。

敬語は複雑な点もあるため、下の記事を確認しておくと安心です。
-
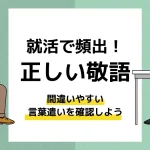
-
就活で頻出!正しい敬語一覧|間違いやすい言葉遣いを確認しよう
就活では、企業説明会や面接、メールのやりとりなど、敬語を使う機会が多くあります。ビジネスマナーのひとつとして、正しい敬語を使うことが重要です。この記事では、就活で頻出する尊敬語や謙譲語の正しい使い方、間違いやすい使い方などを解説します。
続きを見る
-
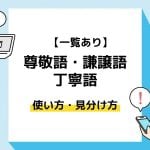
-
尊敬語・謙譲語・丁寧語の違いをマスター!使い方や見分け方を紹介【一覧あり】
敬語は尊敬語・謙譲語・丁寧語の3種類にわけられます。敬意を示す相手や行動によって使う表現が異なるため、違いを確認しておきましょう。適切に使いわけることで、円滑なコミュニケーションが図れます。
続きを見る
エントリーシートで間違いやすい敬語表現一覧
エントリーシートで使われる敬語で、間違いやすい表現を紹介します。丁寧に書こうとするあまり、誤った敬語を使用していることもあるため、確認してみましょう。

「である調」でも「おっしゃる」などの敬語表現は用いることがあるので、チェックしておきましょう!
| 誤用表現 | 正しい表現 | 解説 |
| おっしゃられる | おっしゃる | 「おっしゃる」は尊敬語であり、 「られる」を重ねると二重敬語になる |
| 拝見させていただく | 拝見する | 「拝見する」は謙譲語であり、 「させていただく」を加えると二重敬語になる |
| 行かさせていただく | 伺う | 「行かさせていただく」は「さ入れ言葉」とされる誤用であり、 正しくは「伺います」や「参ります」を使用する |
| 僕/自分 | 私/わたくし | 「僕」や「自分」はカジュアルな表現であり、 ビジネスの場では「私」や「わたくし」を使用する |
| 御社(書き言葉) | 貴社 | 書類やメールでは「貴社」を使用し、 口頭では「御社」を使用する |
| さっき | 先ほど | 「さっき」はカジュアルな表現であり、 ビジネスの場では「先ほど」を使用する |
| わからない | 存じ上げない | 「わからない」はカジュアルな表現であり、 ビジネスの場では「存じ上げない」を使用する |
-
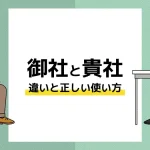
-
御社と貴社の違いは?面接や履歴書、メールでの正しい使い方を解説
面接など言葉にするときは「御社」、履歴書やメールで文章にするときは「貴社」です。言い間違えをしやすい言葉ですが、一般常識のひとつであるため、できるだけ正しい使い方ができるよう意識しましょう。
続きを見る
-
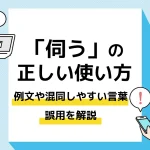
-
敬語表現「伺う」の正しい使い方!例文や混同しやすい言葉、誤用を解説
「伺う」は「行く(訪問する)」「聞く」「尋ねる(確認する)」の3つの意味を持つ敬語表現です。この記事では、「伺う」の意味や使い方、注意点を解説します。間違えやすい二重敬語の例や言い換え表現も紹介していますので、参考にしてみてください。
続きを見る
エントリーシートは文体よりも「中身」!
エントリーシートは、読み手に伝わりやすい文章で作成するのも大切ですが、重要なのは内容です。企業の採用担当者はエントリーシートの内容を見て、人柄や自社で活躍できるかを知りたいと考えています。
限られた文字数のなかで、自分の強みや志望動機を効果的に伝えるためには、具体的なエピソードや成果を交えるのがおすすめです。伝えたいことを簡潔に、要点を押さえた文章構成を意識してエントリーシートを作成してみましょう。
-
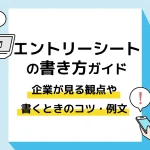
-
エントリーシートの書き方ガイド!企業が見る観点や書くときのコツ・例文を項目別で紹介
インターンや就活で提出するエントリーシート(ES)は、企業に自身のスキルや特徴を知ってもらうための重要な書類です。この記事では、エントリーシートの書き方のポイントや項目別の例文、基本情報や学歴の記入方法などを詳しく解説します。
続きを見る
よくある質問
エントリーシートは「ですます」「だ・である」のどっちの語尾が正解ですか?
語尾に正解はないので、どちらでもかまいません。「ですます調」は丁寧で柔らかい印象を与えるため、無難な選択でしょう。一方、「である調」は断定的で力強い印象を与えるため、自信や論理性を強調したい場合に適しています。ただし、文体は統一することが重要です。
エントリーシートを「ですます調」で書く際の注意点はありますか?
「ですます調」は丁寧な印象を与えますが、語尾が単調になりやすい点に注意が必要です。同じ語尾が続かないように工夫し、文章にリズムを持たせるように意識してみましょう。
エントリーシートで体言止めを使用していいですか?
体言止めの使用は可能であり、文章にリズムや印象を与える効果があります。ただし、多用すると文章が軽くなったり、意味が曖昧になったりする恐れがあるため、適度に使用するのが望ましいです。
エントリーシートを「である調」で書く際の注意点はありますか?
「である調」は断定的で力強い印象を与えますが、読み手によっては堅苦しいと感じられる可能性がある点に注意しましょう。