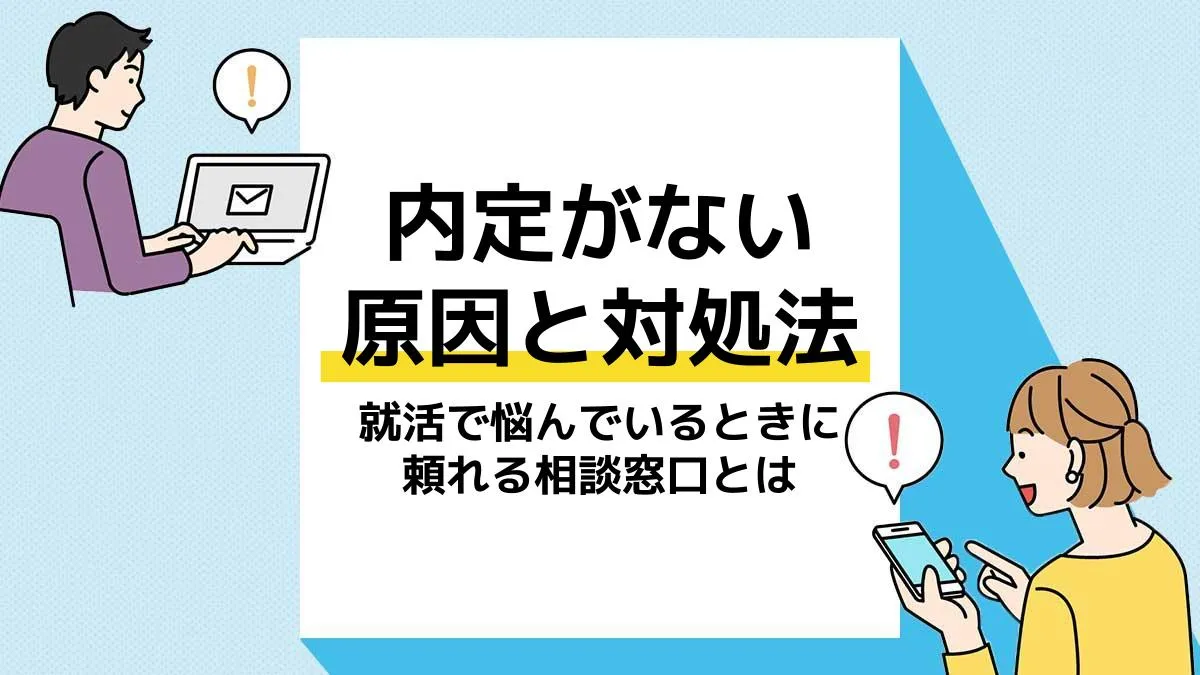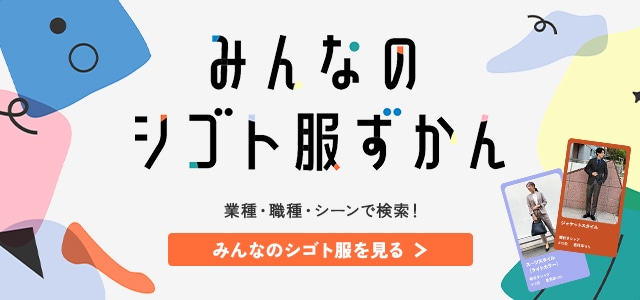内定がない状態のことは「無い内定」と呼ばれたり、NNT(Nai Nai Tei)と略されることもあります。また、無い内定は「内々定」にかけた言葉として、SNSなどインターネット上で使われることもあるようです。
内定がない状態から抜け出すには、内定がない原因を把握し、適切な行動と対策を行うことが大切です。就活のゴールは単に内定を獲得することではありません。
自分に合う企業を見つけて納得できるかたちで就活を終えるために、まずは現状を振り返り、やるべき行動と対策をしっかり行っていきましょう!
この記事でわかること
- 内定がない原因は、就活の準備段階・書類・面接のフェーズによって異なることがある
- 内定がないことに悩んだら、キャリア支援センターなどに相談するのがおすすめ
- 企業によっては、秋採用や冬採用、通年採用を行っている
目次[表示]
内定がない...…あせらず正しい対策と行動をすれば内定可能!
自分には内定がないのに、友人たちは次々と内定をもらっていて、不安やあせりを感じてしまいます……。


自分だけ内定が出ていないと、気持ちが落ち込んでしまいますよね。でも、内定がないからといって「自分には価値がない」とネガティブに捉える必要はありませんよ!
内定を得られていない理由は、必ずしも能力や経験の不足によるものとは限りません。能力や経験が十分であっても、企業との相性が合わなかったり、タイミングが合わなかったりしたことで、内定を得られていない可能性もあります。
内定を早く獲得したいからといって、あせった状態で就活を続けると判断力が鈍り、満足のいく結果を得にくくなります。

冷静になり、適切な対策と行動は何かを考え、自分に合う企業からの内定を目指しましょう。
一般的な内定の時期や割合
就活の進め方やスケジュールは人により異なるため、「いつまでに内定を得ていなければならない」といったものはありません。ここでは、データをもとに内定の時期や割合について紹介します。
初内定の時期は「卒業年前年の3月」が多い
株式会社リクルートの就活の情報発信を目的とした組織「就職みらい研究所」が行った「就職プロセス調査(2025年卒)」によると、25卒の学生が初めて内定を取得する時期で最も多かったのは、15.5%で卒業前年度の3月でした。次いで、15.4%で卒業年度の4月となっています。
なお、「就職確定先から内定を取得した時期(内定を決定した時期)」は、17.3%で卒業年度の4月が最も多い結果となりました。
6月で約2割、7月で約1割の学生は内定がない
「就職プロセス調査(2025年卒)」にある、月ごとの内定率の推移を見ると、5月1日時点で72.4%、6月1日時点で82.4%、7月1日時点で88.0%となっています。
この結果を反対から見ると、内定がない学生は5月1日時点で約3割、6月は約2割、7月1日時点で約1割であるとわかります。
この結果はあくまでも目安であり、就活スケジュールは人それぞれです。今からでも戦略を練り直し、内定を勝ち取れる可能性は十分にあります。
内定がないまま卒業する人の割合とは?
「就職プロセス調査(2025年卒)」にある、月ごとの内定率の推移を見ると、25卒における3月卒業時点の就職内定率は98.8%となっていました。このことから、1.2%の人は内定がないまま卒業していると考えられます。
【準備編】内定がない原因と対処法
まずは、就活の準備不足による、内定がない原因と対処法を紹介します。
自分の強みや弱みを正しく理解していない
自分の強みや弱みを正しく理解できておらず、自分らしいアピールができていないことが考えられます。
自分の強みを伝える際は、具体的なできごとを交えて納得感のあるエピソードにしましょう。これには、単に自己分析ツールなどで強みを把握するだけでなく、過去の経験を客観的に分析することが重要です。
また、強みや弱みを自分視点だけで判断している場合、他者から見える自分の強みや弱みとズレが生じている可能性があります。
【対処法】自己分析・他己分析で客観的に自分を理解する
すでに自己分析をしている場合でも、客観的に自分を理解できていないケースがあります。そのため、再度自己分析を行い、自分の強みや弱みを深掘りしていきましょう。
また、家族や友人などに自分の特徴や性格を聞いて分析する「他己分析」も効果的です。自分の強みと弱み、大切にしている価値観などを把握することは、企業選びや自己PR・志望動機の作成に役立ちます。
-
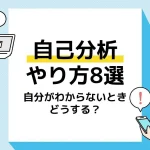
-
今すぐできる自己分析のやり方8選|無料診断ツールや強みが見つからない理由も紹介
自己分析を行うことで、自分に合う業界・職種・企業が見つけやすくなります。それだけではなく、ESや面接で頻出する志望動機や自己PRなどで、独自性・具体性のあるエピソードを考えられるでしょう。就活が本格化する前に、自己分析を進めていきましょう。
-
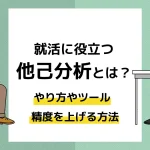
-
就活に役立つ「他己分析」とは?やり方やおすすめツール、精度を上げるコツを紹介
他己分析とは、家族や友人などの第三者に自分の特徴や印象を聞いて、自分を分析する方法のことです。客観的な視点が入ることで、自己分析の精度を上げるなどの効果があります。この記事では、他己分析のやり方やメリット、おすすめのツールなどを紹介します。
キャリアプランが明確でない
「何のために働きたいのか」「仕事を通じて何を達成したいのか」など、自身が希望するキャリアや将来像が明確でない場合、企業選びや自己PRに迷いが生じやすくなります。
例えば、内定をあせる気持ちから、業界・企業を深く考えて選ばずにエントリーしている方もいるでしょう。しかし、あせりや迷いのある状態で選考に進むと、志望理由や自己PRが抽象的になりやすく、選考通過が難しくなるかもしれません。
【対処法】就活の軸を考え直す
就活の軸とは、企業・業界選びで重視する自分なりの価値観や譲れない条件のことです。1~3個の就活の軸を考え、キャリアプランを明確にしてみましょう。
すでに就活の軸を決めているかもしれませんが、就活を進めていくなかで当初考えていた軸が自分に合っていないと感じることはよくあります。そんなときは、改めて就活の軸を考え直すことがおすすめです。
就活の軸を決める際に、次のような質問を自分へ投げかけて考えてみましょう。
- 自分が人生で何を成し遂げたいか
- どんな仕事にやりがいを感じるのか
- どんな環境で働きたいか
- どんな人と働きたいか
- ワークライフバランスをどのように実現したいか
就活の軸を明確にすると、自分に合う企業が探しやすくなるだけでなく、自己PRや志望動機などの回答に一貫性を持たせられ、説得力のあるアピールがしやすくなります。
-

-
就活の軸の決め方|見つからないときの考え方や業界別・職種別の例を紹介
就活の軸とは、企業や業界を選ぶうえで譲れない条件を指します。就活の軸を決めることで、自分なりの思いを中心に企業を選び、選考に臨むことができます。今はまだ決められていない方も、自己分析や他己分析などをすることで見つけられるでしょう。
倍率の高い企業や大手企業ばかりエントリーしている
倍率の高い人気企業や大手企業ばかりにエントリーしていることで、内定を獲得する難易度が高くなっているケースもあるでしょう。特に、自分のスキルや経験に合致していない企業に応募している場合、内定獲得のハードルが上がります。
また、「人気があるから」「大手だから」という理由だけでエントリーしていると、志望動機が抽象的になりやすく、面接官から深掘り質問をされた際の受け答えが難しくなります。
【対処法】今一度大手がいい理由を深掘りして将来を考える
「大手がいい」「有名企業がいい」という理由を今一度深掘りしてみましょう。
大手企業、有名企業に絞って選考を受けることに問題はないですが、「大手だから」といった理由だけでは、志望動機や入社後にしたいことに深みが出ないというリスクがあります。この状態のまま就活を継続すると、内定がない状態が続く可能性もあるでしょう。
ほかにも、「大手がいい」といった理由だけでは、入社後に「大手なのに想定していた働き方と違った」などミスマッチも起こりやすくなります。ミスマッチは、早期退職につながることもあるでしょう。

自分が名前を知らないけど、実は有名企業、大手企業、その業界では急成長中といった企業もたくさんあるはずです!「自分は知らなかったけど、実はすごい企業」「地元では有名企業」「中小企業だけど、実は有名なあの商品を作っている」といった企業を探してみるのもいいかもしれませんね。
業界・業種を絞り過ぎていて、応募数が少ない
応募数が少ないことで内定を得られていないケースもあるでしょう。特定の業界・業種にしか目を向けていない場合、応募できる企業の範囲が限られてしまいます。
また、業界・業種を絞っていると、選考を通過できなかった場合の選択肢も少なくなります。
【対処法】応募数を増やす
これまでの応募数が少ないと感じているなら、少し視野を広げて、応募数を増やすことを検討してみましょう。ただし、やみくもに応募数を増やすわけではありません。自分の強みやキャリアプラン、就活の軸に合う業界・企業を見つけて、エントリーすることが大切です。
ただし、やみくもにエントリー数を増やすことは避けましょう。今一度自己分析をしてみて、「今まで気づかなかったけど、こんな業界・職種に向いているかもしれない」といったことを探してみるのがおすすめです。
適性検査の対策が十分ではない
企業により異なりますが、適性検査は書類選考と同時、または一次面接の前後で実施されることが一般的です。書類や面接の対策がしっかりできていても、適性検査の結果次第では、選考に通過できないことも考えられます。
【対処法】本などで能力検査・性格検査の対策をする
適性検査には、能力検査と性格検査があり、どちらも対策しておきましょう。
能力検査は、国語や数学などの問題が出題されます。過去に習ったことがあるものでも解法を思い出せない可能性があるので対策が必要です。
性格検査は能力検査のような対策は不要ではありますが、内容をある程度把握しておき、回答していくコツは把握しておきましょう。
適性検査の種類はSPIや玉手箱、GABなどさまざまであるため、企業が行う適性検査に合った対策をしましょう。また、就活情報サイトなどでは、企業が実施している適性検査の種類を把握できることがあります。

適性検査の対策方法などは、こちらの記事で詳しく解説しています。
-
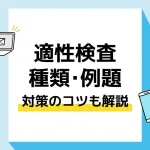
-
就活の適性検査の種類・例題|種類と対策のコツをわかりやすく解説
適性検査には、能力検査と性格検査の両方が実施されることが一般的です。SPIや玉手箱などの種類がありますが、出題傾向や解答方法などが異なります。選考に通過できるよう、企業が実施する適性検査を調べ、対策を進めていきましょう。
-
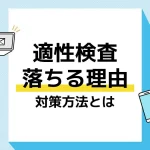
-
【就活】適性検査で落ちる理由とは?能力検査・性格検査それぞれの対策法を解説
適性検査に落ちる理由としては、能力検査で不正解や未解答が多かっただけではなく、性格検査による可能性もあります。なぜ適性検査に落ちてしまうのか、どれくらいの人が落ちてしまうのか、どうすれば突破できるのかを把握して、今後の選考に臨みましょう。
【書類選考編】内定がない原因と対処法
次に、ES(エントリーシート)や履歴書に関する原因と対処法を紹介します。

ここで紹介するポイントは、次の段階の面接でも当てはまるため、「書類選考は通過するけど、面接ではなかなか通過できない」という方もチェックしてみてください。
企業目線が不足している
自己分析をしっかり行っていたとしても、アピールする内容が企業が求める能力とマッチしていない場合があります。例えば、企業側が求める人物像が「コミュニケーション能力が高く積極的な人」の場合、「探究心」をアピールしても、ミスマッチかもしれません。
自己分析や志望動機では、企業が求める人物像と自分の強みを結びつけてアピールすることが大切です。
【対処法】企業研究をやり直す
企業研究は、志望する企業への理解を深めるために必要な準備です。企業のことを理解し、自分がその企業で活躍するイメージを採用担当者にアピールすることで、選考通過の可能性が高くなるでしょう。
改めて企業研究を行い、企業が求める人物像、企業理念、経営理念、将来のビジョン、事業内容などをしっかり確認しておきましょう。
-
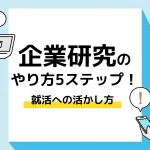
-
企業研究のやり方5ステップ!ノート・シートの作成方法や就活への活かし方を解説
就活における企業研究は、企業の詳細な情報を収集し分析するプロセスです。この記事では、企業研究のやり方を5ステップで解説します。情報収集の方法や企業研究で得た情報を就活で活かすポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
-
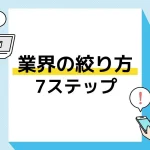
-
就活での業界の絞り方7選!自分に合った方法で就活を進めよう
志望する業界は3つ前後に絞るのがおすすめです。1種類に絞ると、エントリーする企業を見つけにくいなど、デメリットを受けやすくなります。業界を絞れないときは、再度自己分析をするなどして、自分に合う業界を見つけましょう。
同じ内容を使い回している
「同じ業界だから」「ばれないから」などの理由で、ESの内容を使い回すことがあるかもしれません。質問によっては使い回せるものもありますが、使い回せないものもあります。
使い回した内容によっては、採用担当者がESを確認したとき、違和感を覚えることも考えられます。例えば、志望企業求める人物像を把握しておらず、ESの内容とマッチしていないときなど、使い回しによる違和感が出てきやすいでしょう。
【対処法】使い回せるもの・そうではないものを理解する
例えばガクチカの場合、「何を頑張ったのか(例:ゼミ活動に力を入れた)」を使いまわすのは問題ないでしょう。しかし、頑張って得たことで企業に活かせることまですべて同じにしてしまうと、企業が求める人物像から外れることがあるため、企業ごとに調整する必要があります。
志望動機は同じ業界、似た企業であっても使い回しは避けましょう。志望動機は独自性を出すことで、自分らしさをアピールできるポイントです。
同じ業界、似たような企業だったとしても、企業風土や求める人物像などは異なるはずです。その企業ならではのポイントを考え、エピソードを再構成しESに反映させることで、選考によい結果が期待できるでしょう。
-
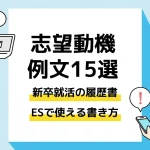
-
理由別の志望動機例文15選|新卒就活の履歴書・ESで使える書き方を解説
新卒就活において「志望動機」はよく聞かれる質問のひとつです。この記事では、新卒の志望動機の書き方、志望動機の例文15選を紹介します。ほかの学生と差別化するための志望動機の例や注意したいポイントも解説していますので、参考にしてみてください。
-
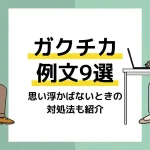
-
【例文9選】ガクチカとは?エピソードが思い浮かばないときの書き方も解説
ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」であり、書類選考や面接の質問で頻出します。アルバイトやゼミなどでの経験をガクチカとして伝えることは可能です。この記事では思い浮かばないときの対処法や、9つの例文などを紹介しています。
【面接編】内定がない原因と対処法
面接でアピールする内容、マナー、立ち振る舞いが原因で、選考に通過できない場合もあるかもしれません。そのようなときの原因と対処法は次のとおりです。
話し方で熱意が伝え切れていない
面接で緊張して声が小さくなる、早口になるなど、わかりにくい話し方によって熱意が伝わりきれていないことも考えられます。
例えば次のような話し方になっている場合は、できる限り改善したうえで面接に臨みましょう。
- 受け答えが曖昧
- 回答内容に矛盾がある
- 目を見て話さない
- 声が小さい
- 反応が薄い
- 早口で聞き取りにくい
- 表情が読み取りにくい
【対処法】面接で話す姿を客観視する
面接に限らず、話し方の癖は自分では気づきにくいポイントのひとつです。自分を客観視する手段としては、次のような方法があります。
- 面接の練習風景をスマートフォンで撮影する
- 友人など複数人で面接の練習をして指摘し合う
- キャリア支援センターで模擬面接をする
スマートフォンなどで撮影すると、自分を客観視して、癖に気づきやすくなります。友人との練習、キャリア支援センターのアドバイザーといった第三者に自分の話す姿を見て客観的な意見をもらうのもおすすめです。
-
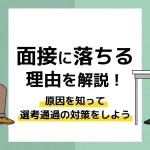
-
面接で落ちる理由を解説!不採用の原因を知って対策をしよう
面接に落ちる理由はさまざまですが、「面接での回答」「身だしなみ・マナー」「話し方」などが考えられます。この記事では、面接で落ちる理由と具体的な対策方法を解説します。面接に落ちる理由を知り、次の面接に向けて対策していきましょう。
-
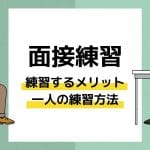
-
本番前にやりたい面接練習!一人でできるやり方や練習しないデメリットも解説
面接の練習をすることで、本番の緊張を軽減できるメリットがあります。練習相手がいなくても、面接練習アプリやYouTubeのシミュレーション動画を活用すると、本番のような練習ができます。
身だしなみが整っていない
身だしなみは、接する相手を不快にさせないための思いやりであり、良好な関係を築くために必要な要素のひとつです。
例えば次のような身だしなみは、ビジネスシーンにマッチしていないという印象になり、選考に影響する可能性があります。
- 服装にシワや汚れがある
- 髪型が乱れている
- 挨拶ができていない
- 敬語が使えない
- 時間を守らない
- 面接での態度が悪い
【対処法】面接に臨む姿を客観視する
面接に臨む前に、次のポイントを確認しておきましょう。
身だしなみのチェックポイント
- 服のサイズは自分の体にあっているか
- 服にシワやホコリがついていないか
- 服やバッグ、シューズにタグはついていないか
- 髪型が乱れていないか
- 爪が長すぎないか
- メイクと服装がマッチしているか
- 髭の剃り残しはないか
- 香水や汗などのニオイはきつくないか
可能であれば、友人や家族など自分以外の人による確認もあると、より身だしなみを客観視しやすくなります。他者によるチェックがあると、身だしなみが乱れている部分などがわかりやすくなるでしょう。

自宅を出る前に全身鏡などでチェックしてみましょう!
-
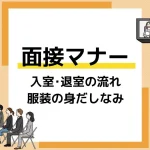
-
面接のマナーが画像付きでわかる!入室・退室・服装の身だしなみをわかりやすく解説
面接のマナーで気をつけたいポイントとして、入室・退室の流れ、言葉遣いなどがあります。特に初めての面接では不安も多いですが、練習を重ねることで緊張感を和らげることが可能です。事前にどんなことに気をつければよいのかをチェックして、自信をもって面接に臨みましょう。
-
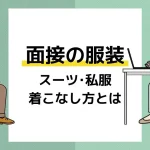
-
面接の服装を画像付きで解説!スーツ・私服・ビジネスカジュアルの着こなしとは
面接で着用する服としては、スーツやビジネスカジュアルなどがあります。どんな服装を洗濯する場合でも、清潔感や統一感が大切です。何を選べばいいのか、どう着こなせばよいのかを把握しておき、自信をもって面接に臨みましょう。
\ビジネスシーンで着用する服装はこちらをチェック!/
想定外の質問に対応できなかった
面接では、志望動機や自己PRといった定番の質問以外にも、少し変わった質問をされることがあります。
少し変わった質問は、どんな質問をされるか事前にわからないため、対策が難しいことがあるかもしれません。思うように回答できなかったことが原因のひとつとなり、選考に影響を与えたことも考えられます。
【対処法】変わった質問の例を見て対策する
採用担当者が変わった質問、面白い質問をする意図としては、「とっさのときどんな対応をするのか知りたい」「思考の柔軟性が知りたい」といったものです。
そのため、想定外の質問だったとしても、できるだけ的確な回答をすることが求められるでしょう。的確な回答をするためには、「こんな質問をされるかも」と想定し、ある程度回答内容を考えておくことが大切です。
変わった質問の例
- 自分を色に例えると?
- 自分を動物に例えると?
- 自分を一言で表すと?
- 友人からどんな人と言われる?
- 無人島にひとつだけ持っていくなら何?
- 幼少期のときはどんな人物だった?
- 最近あった面白いできごとは?
- 苦手な人はどんな人? など
-
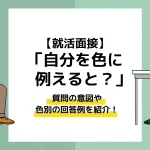
-
【面接】「自分を色に例えると?」の答え方|質問の意図や色別の回答例を紹介!
就活の面接で「自分を色に例えると」と質問されたときは、何色を答えるかよりも「なぜその色を選んだか」という理由が重要です。この記事では、「自分を色に例えると」の回答の考え方や企業側が質問する理由、色別の回答例文などを紹介します。
-
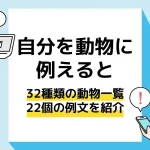
-
「自分を動物に例えると?」32種類の特徴一覧と22個の例文を紹介【就活面接】
就活の面接で「自分を動物に例えると」という質問が行われることがあります。これは、人物像や思考の柔軟性などを知る目的だと考えられます。どの動物を選べばいいのか、どんな回答をすればよいのかを紹介します。
-
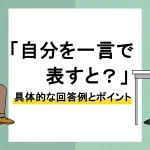
-
面接で「自分を一言で表すと?」と聞かれたら?具体的な回答例とポイントを紹介
「自分を一言で表すと?」への回答は、自分の特徴や強み、経験を基にした言葉を選び、語彙を工夫することがポイントです。この記事では、この質問をする企業側の意図や、自分を表す言葉・ネタの例、面接での効果的な回答方法や例文を紹介します。
内定がないことに悩んだら。頼れる相談窓口や人を知っておこう
内定がない状態が続くと、落ち込んでしまうこともあるでしょう。不安などネガティブな気持ちがある方は一人で抱え込まず、誰かに相談をしてみることをおすすめします。
内定がなくメンタルに影響が出そうなときは、次の場所や人に相談してみましょう。
キャリア支援センター
キャリア支援センターは、学内にある就活の相談ができる場所です。
アドバイザーに現在の状況を伝えて、どんなところを改善すればよいか相談してみるのがおすすめです。ESの添削、面接練習などもできるので、ぜひ利用してみましょう。
ハローワーク
ハローワークには「新卒応援ハローワーク」という施設があり、大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方利用できます。ここでは、就活の進め方や求人の選び方などを相談できるほか、ES作成、面接対策も行っています。
ハローワークであるため、選考の相談以外にも求人を探すこともできます。新卒応援ハローワークは全国各地にあるので、近くにある方は一度利用することも検討してみてください。
就活エージェント
就活エージェントとは、キャリアアドバイザーが就活を支援してくれるサービスです。「職業安定法第4条」により、厚生労働省から認可された職業紹介事業者であるため、安心して利用できます。
就活エージェントでは、キャリアアドバイザーとの相性が重要です。初回面談の際に、話しやすさ、信頼できるかを確認してみましょう。
オンライン面談やLINEなどのツールでやりとりできる就活エージェントであれば、学業やアルバイト、就活で忙しい方にとって利用しやすいはずです。
-
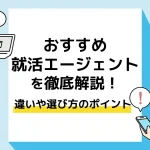
-
おすすめ就活エージェントを徹底解説!違いや選び方のポイントを紹介
就活エージェントは、専任のアドバイザーから就活全般のサポートを受けられるサービスで、学生は無料で利用できることが特徴です。この記事では就活エージェントの概要や選び方、メリット・デメリット、おすすめの就活エージェントなどを紹介しています。
友人・先輩・家族などの頼れる人
友人や先輩、家族は、「ESの添削や面接のアドバイスをくれる」「仕事を紹介してくれる」というわけではないが、頼れる人に相談する、話を聞いてもらうことも大切です。
自分の悩みを聞いてもらうだけでも気持ちがすっきりして、ポジティブに就活ができる人もいるはずです。社会人として働いている先輩のなかには、就活でなかなか内定をもらえず苦労した経験があり、今の自分に近い状況だった人もいるでしょう。
「内定がもらえるわけではないから意味がない」と人に相談しないのではなく、気分転換のために人に悩みを打ち明けてみるのもいいかもしれません。
夏までに内定を獲得できなかった場合は秋採用・冬採用に挑戦しよう!
すでに夏や秋になり、「友人はみんな内定をもらっているのに、自分だけ内定がない」と悩んでいる方もいるかもしれません。
新卒を対象とした就活では、春から夏にかけて採用活動を行っている企業が多いですが、なかには秋採用や冬採用、通年採用を実施していることもあります。
そのため「夏までに内定がもらえなかった」と悩むよりも、就活情報サイトなどを活用して、秋採用や冬採用を実施している企業を探してみましょう。

企業の規模や職種を問わず、秋採用や冬採用、通年採用を実施していることがあります。
-
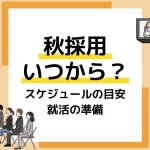
-
秋採用はいつからスタート?スケジュールの目安・企業の探し方・就活の準備を解説
秋採用は、春・夏の採用活動が終了したあとに実施されます。夏から継続して就活をしている人以外にも、学業など就活以外のことを優先していた人、公務員試験に挑戦した人、海外留学をしていた人などさまざまな人が参加しています。準備をしっかりと行ったうえで、選考に臨みましょう。
内定がないまま卒業したあとはどうなる?
内定がないまま卒業したときの選択肢としては、次のようなものがあります。
- 大学院への進学
- 非正規社員として就職(働きながら転職を目指す)
- 就職留年(就活を目的に留年をする) など
大学院へ進学した場合は、2年後または3年後に再び就職活動を行うことになります。いずれの選択肢も、自分が本当に働きたいと思える企業を探すことに変わりはありません。

卒業までまだ期間があるなら、諦めるよりも就活を継続していくのも選択肢のひとつです。
卒業から3年以内であれば新卒枠で応募できる場合がある
「内定がないまま卒業したら、新卒ではなくなり意味がなくなってしまう」と思う方もいるかもしれませんが、厚生労働省では、企業に対して「卒業から3年以内の人は、新卒枠で応募できるようにする」といったことを呼びかけています。
これにより、企業によっては卒業後に新卒として応募できる可能性があります。

内定がないまま卒業しても、就活を継続することで自分に合う企業が見つけられるかもしれませんね。
一人で悩み続けていると心身に負担がかかるので相談をすることも大切
内定が得られない状況が続けば、どんな人でも心身に負担がかかる状態になるでしょう。体調不良になったり、眠れなかったり、講義に集中できなかったりする日もあるはずです。
つらいときは、友人や家族、キャリア支援センターのアドバイザーなどに相談することも検討してみてください。

ときには、短期間でも就活から距離をおいて友人と気晴らしをするのもいいかもしれません。悩みを聞いてもらうだけでも、気持ちがすっきりすることがありますよ。
よくある質問
内定がない人の特徴を教えてください
内定がない人の共通点として、次のようなことが考えられます。
・自分の強みや弱みを正しく理解していない
・キャリアプランが明確でない
・倍率の高い企業や大手企業ばかりエントリーしている
・業界・業種を絞り過ぎていて、応募数が少ない
・適性検査の対策が十分ではない
・企業目線が不足している
・同じ内容を使い回している
・話し方で熱意が伝え切れていない
・身だしなみが整っていない
・想定外の質問に対応できなかった
それぞれの原因と対処法については、「【準備編】内定がない原因と対処法」「【書類選考編】内定がない原因と対処法」「【面接編】内定がない原因と対処法」で解説しています。
内定がないときはどうすればいいですか?
次回選考を受けるときに向けて、次のような対策をしておきましょう。
・自己分析・他己分析で客観的に自分を理解する
・就活の軸を考え直す
・今一度大手がいい理由を深掘りして将来を考える
・応募数を増やす
・本などで能力検査・性格検査の対策をする
・企業研究をやり直す
・ES・面接の回答で使い回せるもの・そうではないものを理解する
・面接で話す姿を客観視する
・面接に臨む姿を客観視する
・変わった質問の例を見て対策する
9月時点で内定がない状態です。何かできることはありますか?
企業によっては秋採用や冬採用を実施しているため、就活を継続して内定獲得を狙っていきましょう。
秋以降にエントリーする場合は、「内定がない原因と対処法」で紹介したことを振り返り、対処をしたうえで選考に臨むことが重要です。夏までの就活を振り返り改善をすることで、内定を獲得しやすくなるはずです。
内定がないときにやってはいけないことはありますか?
「◯◯をしたから内定をもらえない」ということはないでしょう。
内定がもらえないからといって、自分に適性がない、または自分の希望とは大きく異なる企業にも多数エントリーをすることは避けたほうがよいかもしれません。
また、明確な理由がないまま応募した企業から内定をもらえた場合でも、「ようやく内定をもらえたから」という理由だけで承諾することも避けたほうがよい場合もあります。一度冷静になり、「自分にはこの企業で働きたいと思う気持ちがあるのか」「自分の適性と、企業が求める人物像はマッチしているのか」なども考えたうえで、承諾するかどうかを考えてみてください。
内定がないまま卒業する人の割合を教えてください
株式会社リクルートの就活の情報発信を目的とした組織「就職みらい研究所」が行った「就職プロセス調査(2025年卒)」にある月ごとの内定率の推移によると、3月卒業時点の数値が98.8%となっています。この結果から、1.2%の人は内定がないまま卒業していると考えられます。
無い内定(NNT)とはどういう意味ですか?
「無い内定(NNT)」とは、内定がない状態を表す言葉です。
NNTは「Nai Nai Tei(無い内定)」の頭文字からなる略語で、SNSの投稿やハッシュタグなどのネット上で使われることがあります。